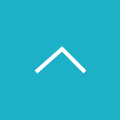WEB発行率80%達成。
導入前の課題
-
手作業で請求書発行を行っており、誤発送のリスクがあった。
-
仕分けや封入などの作業量が多く、またダブルチェックを行うため、スタッフの負担やコストが大きかった。
-
各拠点が異なる方法で請求書発行を行っており、作業方法の統一ができていなかった。
導入の効果
-
請求書発行に関する作業量が大幅に減り、50%のコスト削減に。
-
請求データが確定した当日午前中に、顧客への案内を行うことが可能になった。
-
請求書発行業務を体系化でき、さらなる業務効率化を目指せる土壌が整った。

| 設立 | 1961年 |
|---|---|
| 資本金 | 72億1,275万円 |
| 従業員数 | 1,702名(2020年3月31日現在) |
| 事業内容 |
プラスチック製食品包装容器の 製造・販売 |
| ホームページ |

生鮮食品や惣菜などを入れるプラスチック製食品包装容器の製造・販売を手がける、中央化学株式会社。
数千にも上る製品ラインナップをもち、さまざまな業態の顧客を数多く抱えるメーカーだ。
そんな同社は、2019年10月に『FNX e-急便 WEB発行サービス(以下、e-急便WEB発行サービス)』を導入し、請求書発行業務を刷新。
プロジェクトを担当した是永氏は、「業務効率化やコスト削減、組織の強化にまでつながりました」と話す。
サービス導入で同社はどう変わったのか、業務部の是永氏、笠氏、金地氏の3名にインタビューした。
数千にも上る製品ラインナップをもち、さまざまな業態の顧客を数多く抱えるメーカーだ。
そんな同社は、2019年10月に『FNX e-急便 WEB発行サービス(以下、e-急便WEB発行サービス)』を導入し、請求書発行業務を刷新。
プロジェクトを担当した是永氏は、「業務効率化やコスト削減、組織の強化にまでつながりました」と話す。
サービス導入で同社はどう変わったのか、業務部の是永氏、笠氏、金地氏の3名にインタビューした。
インタビュイープロフィール
営業本部業務部 関西業務課長兼業務課 是永 様
営業本部業務部 九州業務課長兼中四国業務課長兼業務課 笠 様
営業本部業務部 関西業務課兼業務課 金地 様
営業本部業務部 九州業務課長兼中四国業務課長兼業務課 笠 様
営業本部業務部 関西業務課兼業務課 金地 様
導入の背景
請求書発行を手作業で行うことで生じるスタッフの負担やコスト、
そして顧客からの信頼を失いかねない誤発送リスクに課題があった
スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで販売されている生鮮食品、惣菜などに使われるプラスチック製食品包装容器を開発・販売している、中央化学株式会社。1957年創業のメーカーで、現在は日本全国に8つの販売拠点と、8つの工場、中国にも現地法人を構えている。
強みは、顧客からの多彩なニーズに応えられること。その製造品目は数千種類にも及ぶという。また、人々の生活スタイルが変化し、家で食事をとる “中食”や“内食”が増加した。これを受けて同社の製品のニーズはさらに高まり、ますますその開発力や柔軟性が評価されている。
そんな同社では、長らく帳票類の発行・郵送作業に課題を感じていたという。
是永氏は、次のように話す。
「これまで当社では、請求書の発行・郵送作業の大部分を各拠点のスタッフが手作業で行っていました。
具体的な流れとしては、注文品のピックアップから出荷までを一括管理している基幹システムに受注登録をし、請求データを作成します。その後、専用プリンターで請求書と内訳明細書を印刷。この2つはミシン目でつながった状態で出力されるので、裁断した後に担当者が仕分けます。そしてようやく封入するのですが、ここでミスを防ぐために仕分けた担当者と別の担当者がダブルチェックを行いつつ封入作業をしております。しかし、サイズが異なる請求書と内訳明細書をひとつひとつ折りたたんだりしているため、かなりの時間がかかっています。
しかも、お客様によって請求締切日が異なるため、請求書を発送するタイミングも異なっています。例えば月末締めの取引先の場合、基本的には月末に締めて翌月の第2営業日の朝に発行しますが、イレギュラー対応を求められるケースも多く、請求書発行に関する一連の作業は常に発生するといっても過言ではないです。用紙代や印刷代などはもちろん、人件費まで考慮したら、非常に大きなコストがかかっていました」。
また、どれだけ慎重に作業をしても、やはり人の手で行うと仕分け間違いや誤発送をゼロにするのは難しいと是永氏は教えてくれた。
強みは、顧客からの多彩なニーズに応えられること。その製造品目は数千種類にも及ぶという。また、人々の生活スタイルが変化し、家で食事をとる “中食”や“内食”が増加した。これを受けて同社の製品のニーズはさらに高まり、ますますその開発力や柔軟性が評価されている。
そんな同社では、長らく帳票類の発行・郵送作業に課題を感じていたという。
是永氏は、次のように話す。
「これまで当社では、請求書の発行・郵送作業の大部分を各拠点のスタッフが手作業で行っていました。
具体的な流れとしては、注文品のピックアップから出荷までを一括管理している基幹システムに受注登録をし、請求データを作成します。その後、専用プリンターで請求書と内訳明細書を印刷。この2つはミシン目でつながった状態で出力されるので、裁断した後に担当者が仕分けます。そしてようやく封入するのですが、ここでミスを防ぐために仕分けた担当者と別の担当者がダブルチェックを行いつつ封入作業をしております。しかし、サイズが異なる請求書と内訳明細書をひとつひとつ折りたたんだりしているため、かなりの時間がかかっています。
しかも、お客様によって請求締切日が異なるため、請求書を発送するタイミングも異なっています。例えば月末締めの取引先の場合、基本的には月末に締めて翌月の第2営業日の朝に発行しますが、イレギュラー対応を求められるケースも多く、請求書発行に関する一連の作業は常に発生するといっても過言ではないです。用紙代や印刷代などはもちろん、人件費まで考慮したら、非常に大きなコストがかかっていました」。
また、どれだけ慎重に作業をしても、やはり人の手で行うと仕分け間違いや誤発送をゼロにするのは難しいと是永氏は教えてくれた。
主なサービス
\BtoB取引のFAX・帳票業務の効率化をサポート/
関連事例
Copyright © NEXWAY Co.,ltd.