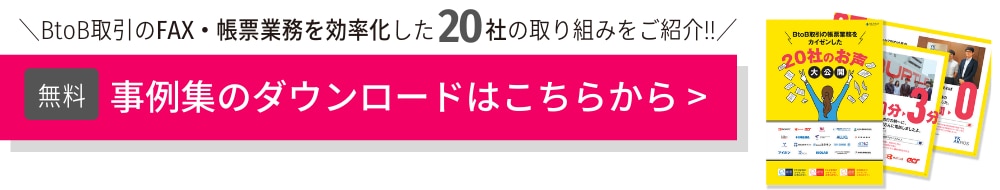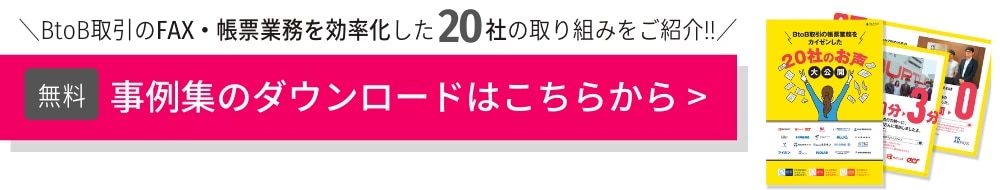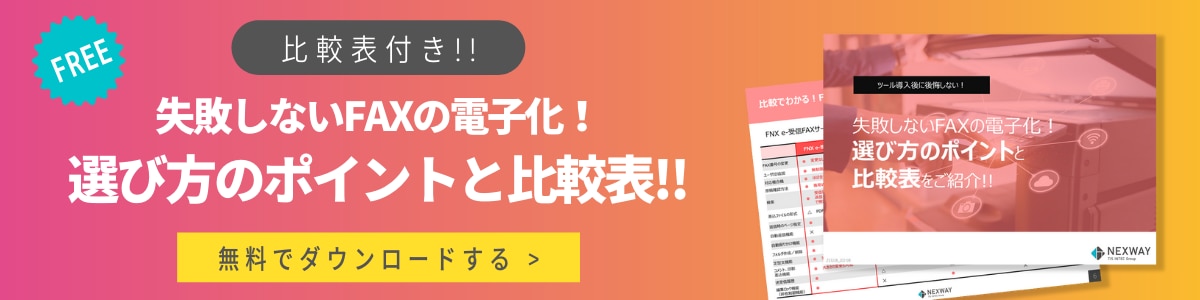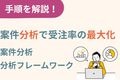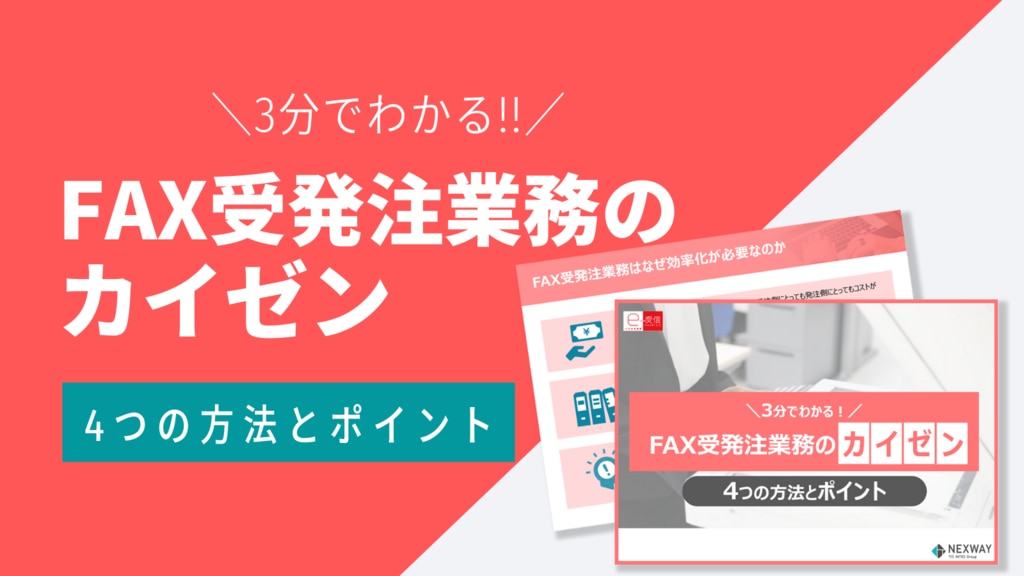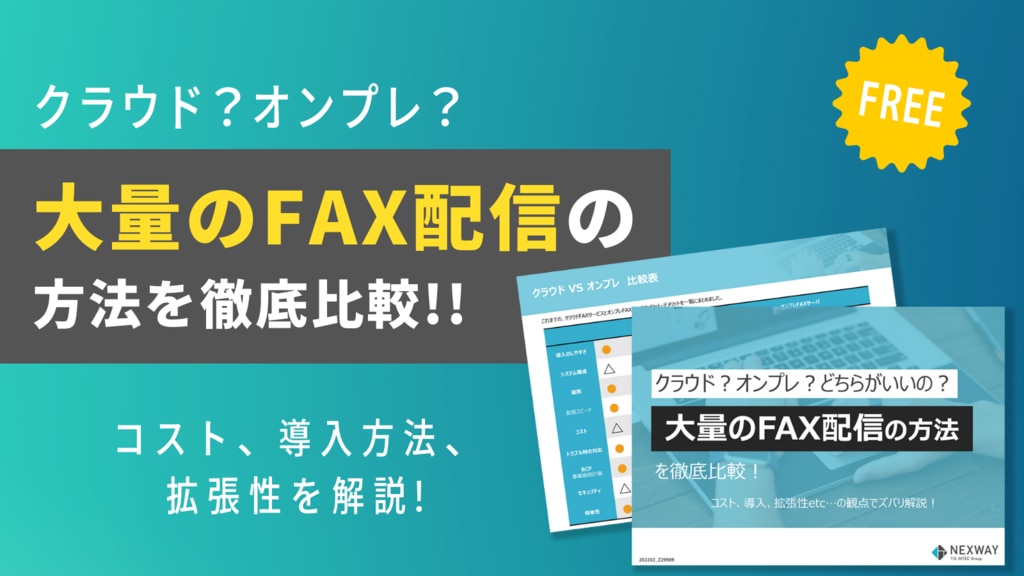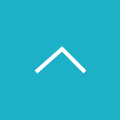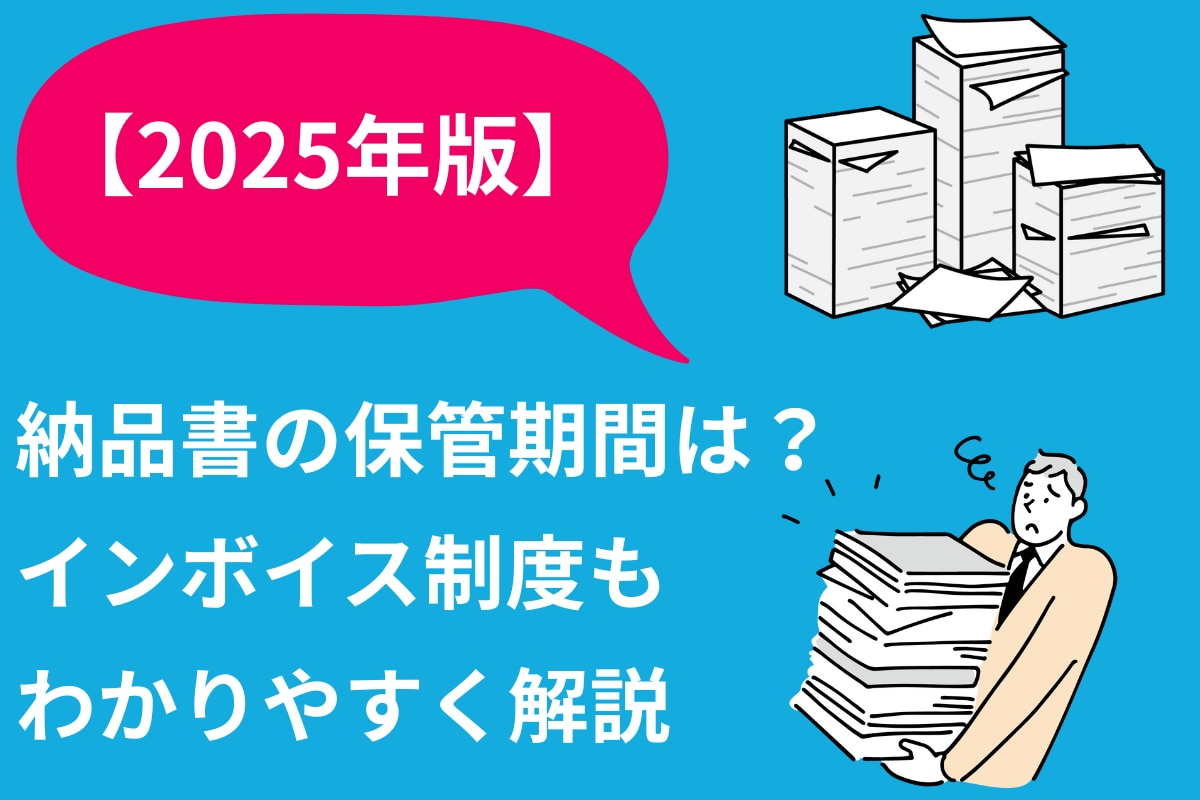
【2025年版】納品書の保管期間は?インボイス制度もわかりやすく解説
「受信したFAXのデータ化でお悩みですか?」
クラウドFAXをAI-OCRと連携して受注業務の完全ペーパーレス化
[詳しくはこちらから]
目次[非表示]
- 1.納品書の保管期間は何年?|法人・個人で異なる保存年数
- 1.1.法人企業は原則7年間の保存義務(法人税法)
- 1.2.個人事業主は青色申告7年、白色申告5年(所得税法)
- 1.3.起算点は「事業年度末から」カウントする
- 1.4.税務調査対策として+1〜2年余裕を持たせるのが一般的
- 2.納品書の保存方法|紙と電子で変わる運用ルール
- 2.1.紙保存の注意点:劣化・紛失・保管スペース
- 2.2.電子保存は“電子取引”扱いになる可能性もある
- 2.3.スキャナ保存と電子取引の違いに注意
- 2.4.PDF保存だけで要件を満たす?実務でよくある勘違い
- 3.電子帳簿保存法と納品書|保存要件と実務の注意点
- 3.1.納品書のPDF送信は「電子取引」に該当する
- 3.2.保存要件3つ(真実性・可視性・検索性)とは?
- 3.3.タイムスタンプや改ざん防止措置が求められる理由
- 3.4.違反になりやすいNG運用例とその対処法
- 4.インボイス制度との関係|納品書は保存対象外?
- 5.他の帳票と比べてどう?|保存期間の一覧まとめ
- 6.納品書の処分タイミングと実務対応
- 7.納品書の保管でよくある疑問Q&A
- 8.まとめ|納品書の保管は「年数・形式・制度」の3軸で考えよう
納品書の保管期間は、法人・個人で異なるだけでなく、電子帳簿保存法やインボイス制度とも関係する重要なポイントです。保存義務を正しく理解しないと、税務調査時のトラブルや法令違反のリスクが生じる可能性もあります。
特に、電子保存のルールが厳格化される中、「納品書は紙で保管すべきか?」「PDFで保存すれば十分か?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、最新の法改正を踏まえ、納品書の適切な保管期間や保存方法をわかりやすく解説します
納品書の保管期間は何年?|法人・個人で異なる保存年数
納品書は、税務上の証憑として重要な帳票のひとつですが、「何年保存すればいいのか?」については、法人・個人、さらには申告方法によって異なります。加えて、保存期間の「起算点」や、税務調査に備えた実務対応など、正確に把握しておきたいポイントも多くあります。ここでは、納品書の法定保存期間の基本から、運用上の注意点までわかりやすく解説します。
法人企業は原則7年間の保存義務(法人税法)
法人税法では、法人が日々の取引を正確に記録・管理し、税務調査などに備えるため、帳簿書類の保存期間を原則7年間と定めています。納品書もその対象に含まれており、請求書や領収書と同様、取引の証拠書類として扱われます。たとえば、仕入先から商品を受け取った証憑として、納品書は税務署からの確認の際に非常に重要な役割を果たします。
保存方法としては紙・電子いずれでも構いませんが、法定保存期間内に原本が劣化・紛失しないよう、適切な管理体制が求められます。とくに電子保存をする場合は、電子帳簿保存法の要件を満たしているか確認し、万が一の調査にも備えられるようにしておくことが重要です。
個人事業主は青色申告7年、白色申告5年(所得税法)
個人事業主における納品書の保存期間は、申告の形式によって異なります。青色申告の場合、法人と同様に7年間の保存が義務付けられ、白色申告では5年間の保存が必要です。これらは所得税法による定めであり、納品書をはじめとした帳票類は、収入や支出の裏付けとして非常に重要な役割を果たします。
特に税務調査の際には、こうした書類が取引の正当性を証明する根拠となるため、記載内容が明確で保存状態が良好であることが求められます。電子化による保存も認められていますが、電子帳簿保存法の要件に準拠しているかの確認は必須です。いざというときの対応力を高めるためにも、整理された状態での管理が望まれます。
起算点は「事業年度末から」カウントする
納品書の保存期間は、その発行日ではなく「属する事業年度の末日」から起算されます。たとえば、2024年6月に発行された納品書が2025年3月期に属する場合、起算点は2025年3月31日です。この基準を理解していないと、保存期間を誤って短く見積もってしまい、法令違反や調査時のトラブルにつながるおそれがあります。
年度をまたいだ取引が多い企業では、帳票管理の混乱を避けるためにも、起算ルールを社内で周知・徹底し、文書管理台帳などで事業年度ごとに分類・記録しておくことが実務上のポイントになります。
税務調査対策として+1〜2年余裕を持たせるのが一般的
税務調査は法定の保存期間内に行われるとは限らず、数年後にさかのぼって実施されるケースもあります。そのため、多くの企業では7年間の保存義務に加えて1〜2年の余裕をもって、8〜10年間納品書を保管する運用が一般的です。
特に過去の取引に関する詳細な説明を求められた際、すでに処分済みであれば、税務署や監査人に十分な根拠を示すことができず、場合によっては不利な判断を受ける可能性も否定できません。保存年限を延ばすことでリスクヘッジとなり、企業の信頼性確保にもつながります。
納品書の保存方法|紙と電子で変わる運用ルール
納品書は「紙で保存するのが当たり前」という時代から、電子保存やクラウド管理への移行が進んでいます。しかし、紙と電子では保存要件や実務上の注意点が大きく異なるため、正しく理解しておかないと法令違反につながるおそれもあり注意が必要です。本章では、納品書の保存方法ごとの違いや、現場でよくある勘違いについて、実務の視点から丁寧に解説します。
紙保存の注意点:劣化・紛失・保管スペース
紙で保存する場合、経年劣化や紛失リスクに加えて、大量の納品書を保管するための物理的スペース確保も重要な課題となります。特に長期保管が求められる納品書は、湿気や直射日光、火災などの災害リスクにも備える必要があり、耐久性の高いファイル、キャビネット、さらには耐火設備の活用が望まれます。また、必要な書類を迅速に取り出せるよう、分類や整理整頓の工夫も重要です。
電子保存は“電子取引”扱いになる可能性もある
納品書をPDFでメール送信した場合、その行為は「電子取引」として扱われる可能性が高くなります。これにより、単にPCフォルダに保存するだけでは不十分で、電子帳簿保存法に定められた保存要件を満たすことが求められます。具体的には、改ざん防止のためのタイムスタンプ付与や、日付・金額などで検索可能な管理体制を整える必要があります。対応が不十分な場合、法令違反と判断される可能性もあるため注意が必要です。
スキャナ保存と電子取引の違いに注意
紙の納品書を受領後にスキャンして保存する場合は「スキャナ保存」となり、受領者が要件を満たす形で保存すれば足ります。一方、最初から電子データでやり取りする「電子取引」は、発行者・受領者の双方に電子帳簿保存法に基づく保存義務が発生します。
両者は保存対象となる起点や要件が異なるため、社内の取引形態に応じた正しい運用が不可欠です。保存方法を誤ると法令違反につながるおそれがあるため、区別して対応することが重要です。
PDF保存だけで要件を満たす?実務でよくある勘違い
「PDFで保存すれば電子化完了」と誤解している企業は少なくありませんが、これは大きな落とし穴です。電子帳簿保存法における電子保存には、真実性・可視性・検索性の3要件を満たすことが求められます。
単にPCにPDFを保存するだけでは、改ざん防止措置や検索機能が不十分なケースが多く、法令違反となるリスクがあります。適切な保存環境を整えたうえで、要件に合った運用が不可欠です。
電子帳簿保存法と納品書|保存要件と実務の注意点
納品書を電子データでやり取り・保存する場合、見落としてはならないのが「電子帳簿保存法」との関係です。単にPDFで保存すればOKというわけではなく、法律で定められた要件を満たしていなければ、電子保存として無効と判断される可能性があります。本章では、納品書が電子帳簿保存法に該当するケースや、満たすべき3つの保存要件、そして現場で注意すべき運用ポイントについて、実例を交えてわかりやすく解説します。
納品書のPDF送信は「電子取引」に該当する
2022年の電子帳簿保存法の改正以降、納品書をPDFでメール送信した場合、それは「電子取引」に該当することが明確化されました。これにより、データを紙に出力して保存するという従来の運用は、原則として認められなくなっています。
電子取引として扱われる以上、電子帳簿保存法に定められた保存要件、すなわち「真実性・可視性・検索性」を確保した上での電子保存が義務づけられています。対応が不十分な場合、税務上の指摘や罰則対象となる可能性があるため、企業は電子化対応の体制を見直し、運用ルールの整備とツール選定を慎重に進める必要があります。
保存要件3つ(真実性・可視性・検索性)とは?
電子帳簿保存法に基づき、電子データとして納品書などを保存する際には、3つの要件を満たす必要があります。1つ目の「真実性」は、保存されたデータが改ざんされていないことを証明するもので、タイムスタンプの付与や訂正・削除履歴の記録によって担保されます。
2つ目の「可視性」は、必要な時にすぐに帳票内容を画面上で確認できる状態であること。3つ目の「検索性」は、日付・金額・取引先名などの項目で帳票データを素早く検索できるようになっていることを指します。これらの要件を満たしていなければ、電子保存と認められず、紙での保存と同様の法的効力が得られません。
タイムスタンプや改ざん防止措置が求められる理由
電子帳簿保存法では、保存されたデータが真正なものであることを証明するために「真実性」の確保が重要とされています。その手段の一つが、発行直後のタイムスタンプ付与です。これは、データがその時点で確定したことを示すもので、後から編集されたり削除されたりしていないことを第三者が確認可能にします。
また、訂正・削除履歴を記録できるシステムを利用することで、変更の履歴が残るため、透明性の高い管理が可能になります。こうした措置を講じることで、税務署や監査機関からの信頼性も向上し、電子保存の正当性が担保されるのです。
違反になりやすいNG運用例とその対処法
電子帳簿保存法におけるNG運用の代表例として、「PDFファイルを単にPCフォルダへ保存するだけ」「ファイル名のルールがバラバラで検索性が担保されていない」「クラウドに保存したものの、対応要件を満たしていない」といったケースが挙げられます。
これらはどれも、真実性・可視性・検索性のいずれかが欠けているため、法令違反と見なされる可能性があります。対策としては、法対応済みの電子保存ツールを導入し、ファイル命名規則の策定や保存手順の明文化を含む社内ルールを構築することが重要です。
インボイス制度との関係|納品書は保存対象外?
2023年から本格施行された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」により、請求書や領収書の保存義務が強化されました。一方で、納品書も保存義務の対象なのか?と疑問に感じる方も多いはずです。実は、納品書は制度上の保存対象には含まれていませんが、実務では注意すべきケースも存在します。この章では、インボイス制度と納品書の関係、そして請求書との一体運用時に気をつけたいポイントを解説します。
納品書はインボイス保存義務の対象ではない
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるために、売手側から交付される「請求書等」の保存を買手側に求める制度です。この「請求書等」には、請求書や領収書が該当しますが、納品書は制度上その対象とは明記されていません。
そのため、原則としてインボイス制度における保存義務の対象外とされています。ただし、取引実態や運用次第では請求書と一体化して扱われるケースもあり、実務では誤解や混同が生じやすいため、帳票ごとの役割を正しく理解したうえで運用することが重要です。
請求書と兼ねた納品書の場合は要注意
納品書と請求書が一体化した帳票は、見た目では納品書であっても、記載内容や目的によっては「請求書」としての性格を持つと判断されることがあります。たとえば、取引金額や税率、支払条件などインボイスに必要な要件が記載されている場合、それは適格請求書(インボイス)として認識され、保存義務の対象となります。
このようなケースでは、納品書であってもインボイス制度に対応した形式と保存方法が求められます。帳票の運用においては、名称だけでなく記載項目の内容を精査し、制度上の位置づけを正確に理解しておくことが重要です。
消費税控除の証憑として求められるケースもある
納品書はインボイス制度上、保存義務の対象ではありませんが、実務では消費税控除の根拠書類として納品書の提示を求められることがあります。特に請求書に不備がある場合や、取引内容の補足として納品書が重視される場面では、証憑(しょうひょう)としての保存価値が高まります。
また、監査法人や税理士が仕入税額控除の適正性を確認する際に、納品書の内容を照合するケースも少なくありません。こうしたリスクに備えるためにも、請求書とあわせて納品書もきちんと保管しておくことが、より安全で信頼性の高い対応といえるでしょう。
他の帳票と比べてどう?|保存期間の一覧まとめ
納品書以外にも、請求書・見積書・契約書など、業務で取り扱う帳票はさまざまあります。実はそれぞれに保存期間や法的根拠が異なり、「なんとなく同じ扱い」で管理していると、思わぬリスクにつながることも。本章では、主要帳票の保存期間を一覧で比較しながら、納品書の位置づけをわかりやすく整理します。帳票ごとの優先度や注意点もあわせてチェックしておきましょう。
納品書/請求書/契約書/見積書などの保存年数比較
各帳票の保存期間は、それぞれ異なる法令に基づいて定められています。たとえば、納品書や請求書は法人税法・所得税法に基づき7年間の保存が必要です。契約書は、商法や民法の観点、あるいは印紙税法の対応を見越して10年間の保存が推奨されます。
一方で、見積書には法的な保存義務はないものの、取引内容の証拠やトラブル発生時の裏付け資料として重要な役割を果たすため、3〜5年程度は任意で保管しておく企業が多いです。帳票ごとの保存方針を明確にすることが、実務対応をスムーズにする鍵となります。
各帳票の法的根拠と実務上の保存メリット
帳票の保存義務は法人税法や所得税法、電子帳簿保存法、さらには印紙税法など多岐にわたる法律に基づいて定められています。たとえば請求書や納品書は税務調査時の重要な証拠となり、契約書は法的なトラブル発生時にその有効性を裏付ける文書となります。
見積書など法的義務のない帳票も、後日条件確認や社内説明に必要となることが多く、業務上のリスク回避に役立ちます。また、帳票を整理・保存することは、過去の業務内容を把握しやすくするという点で、業務フローの見直しやDX推進にも大きく貢献します。
保存義務のない帳票も「残すべき理由」がある
保存義務が法律で明示されていない帳票であっても、実務上では多くの場合、一定期間保管されることが一般的です。たとえば見積書や打ち合わせメモ、仕様書などは、将来的に契約内容や取引条件に関する確認が必要となった際に重要な役割を果たします。
過去の見積条件をもとに再契約が行われることや、社内での説明責任を果たす材料として活用されるケースもあります。万が一のトラブルや誤解を未然に防ぐためにも、保存義務の有無にかかわらず、業務上の重要度を見極めて保管しておく姿勢が求められます。
納品書の処分タイミングと実務対応
納品書の保存期間を過ぎた後、「いつ・どうやって処分すべきか?」という判断に迷うことは少なくありません。特に税務調査や訴訟リスクを考えると、慎重な対応が求められます。また、電子化やクラウド移行を進めた企業にとっては、紙原本の扱いも課題になりがちです。この章では、保存期間終了後の適切な処分時期や方法、実務で押さえておくべき対応例を具体的に紹介します。
保存期間を過ぎた後、いつ・どう処分するか
納品書は保存期間を経過すれば原則として廃棄しても差し支えありませんが、税務調査や会計監査が数年遅れて行われる可能性を考慮し、即時処分を避ける企業も少なくありません。実務では、事業年度ごとに一括して整理・廃棄する対応が一般的で、一定の余裕を持って保存することで万が一に備える体制が整います。廃棄の際には、処分日を記録し、必要に応じて廃棄証明を残すと安心です。
情報漏えいリスクを防ぐための安全な廃棄方法
納品書の廃棄時には、情報漏えいリスクを最大限に抑えるための措置が欠かせません。紙の場合は、内容が復元できないようクロスカット対応のシュレッダーで処理する、あるいは情報処理業者へ機密文書処分を依頼するのが望ましいです。
電子データについては、ゴミ箱に入れるだけでは不十分であり、専用のデータ抹消ソフトや完全削除機能を使って復元不可能な状態にしてから処分する必要があります。処分記録を残しておくことで、コンプライアンス対応としても安心です。
クラウド移行時の紙原本の扱いはどうする?
納品書をスキャナ保存してクラウド上で管理する場合でも、すぐに紙の原本を廃棄するのではなく、一定期間保管する運用が一般的です。たとえば、スキャン後1年間は原本を保管するなど、明確な社内ルールを定めておくことで、トラブル発生時にも迅速な対応が可能になります。
特にスキャナ保存における法的要件を十分に満たしていないケースでは、紙原本の存在が保険的な役割を果たします。保管期間中は湿気や破損に注意して、適切な状態で管理することも重要です。
納品書の保管でよくある疑問Q&A
納品書の保管に関しては、「紙はすぐ捨てていいの?」「請求書と一緒になっていたらどう扱う?」など、細かい部分で疑問を感じるケースが多いものです。この章では、実務担当者からよく寄せられる質問をピックアップし、Q&A形式でわかりやすく解説します。運用上の不安を解消し、自信を持って対応できるようにしましょう。
電子保存すれば紙は処分しても問題ない?
電子帳簿保存法の要件を満たしている場合、納品書を電子データで正しく保存すれば、紙の原本を処分しても法的には問題ありません。要件としては、タイムスタンプによる真実性の確保や、日付・金額・取引先名での検索性の確保が必要です。
可視性も含めて3要件を満たしていることが前提となります。保存環境が不十分なまま紙を廃棄してしまうと、調査時に証憑として認められないリスクがあるため、十分な確認と運用ルールの整備が求められます。
納品書と請求書が一体化している場合の保存ルールは?
納品書と請求書が一つの帳票としてまとめられている場合、その内容が請求書としての記載事項を満たしていれば、「請求書」として扱われます。特に取引金額、消費税率、支払期限などインボイス制度の適格請求書に必要な要素を含んでいると、インボイスとしての保存義務が発生します。このため、帳票のタイトルにかかわらず、その内容を確認し、形式ではなく実質的な役割で判断して保存区分を決めることが重要です。
納品書を紛失したら税務上どうなる?
納品書を1枚紛失した程度では即座に大きな問題にはなりませんが、帳票管理の信頼性が疑われるきっかけになり得ます。税務調査の際に資料提出を求められたときに、納品書がない状態では取引の正当性を証明しにくくなるため、再発行の依頼や取引記録・請求書・契約書などの関連資料で補完することが重要です。また、同様のミスが繰り返されると、組織としての帳簿管理体制が不備と判断され、調査が厳格化される可能性もあるため、日常的な管理精度の向上も欠かせません。
取引先が紙を要求してきたときの対応は?
電子保存が主流となる中でも、業種や企業文化によっては紙での納品書を引き続き希望する取引先も存在します。このような場合、一方的に電子化を進めるのではなく、取引先の意向を尊重しながら柔軟に対応することが重要です。
たとえば、電子データを基本としつつ、必要に応じて紙でも納品書を発行する“ハイブリッド運用”を導入する企業も増えています。取引先との信頼関係を損なわないよう、紙対応のコストや工数も見積もりつつ、長期的には電子化移行の協議を進めていく姿勢が求められます。
まとめ|納品書の保管は「年数・形式・制度」の3軸で考えよう
納品書の保管は、単に法定年数を守るだけでは不十分です。紙か電子かという形式の選択に加えて、電子帳簿保存法やインボイス制度といった関連法令への対応も考慮する必要があります。自社の業務フローや取引先の要望に応じた柔軟な運用体制を構築し、形式的・法的要件の両面を満たす保管ルールを整備することが重要です。2025年以降も変化し続ける制度に対応できるよう、定期的な見直しと改善を意識した取り組みが求められます。
FAXの電子化についてご相談したい方はこちら