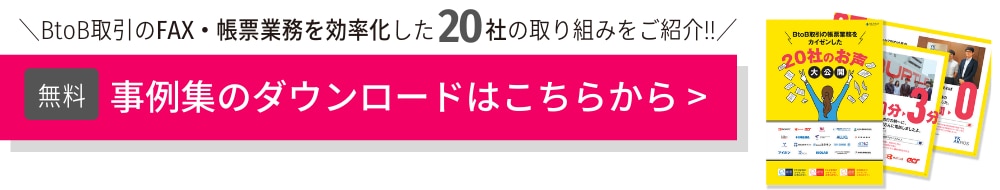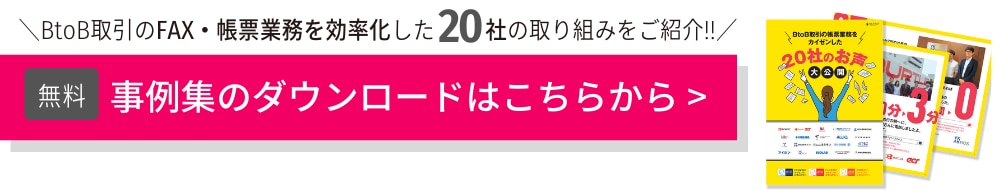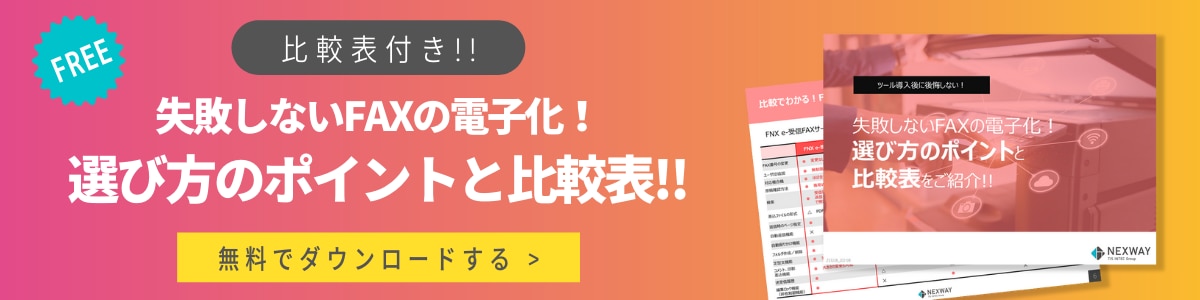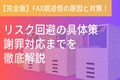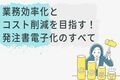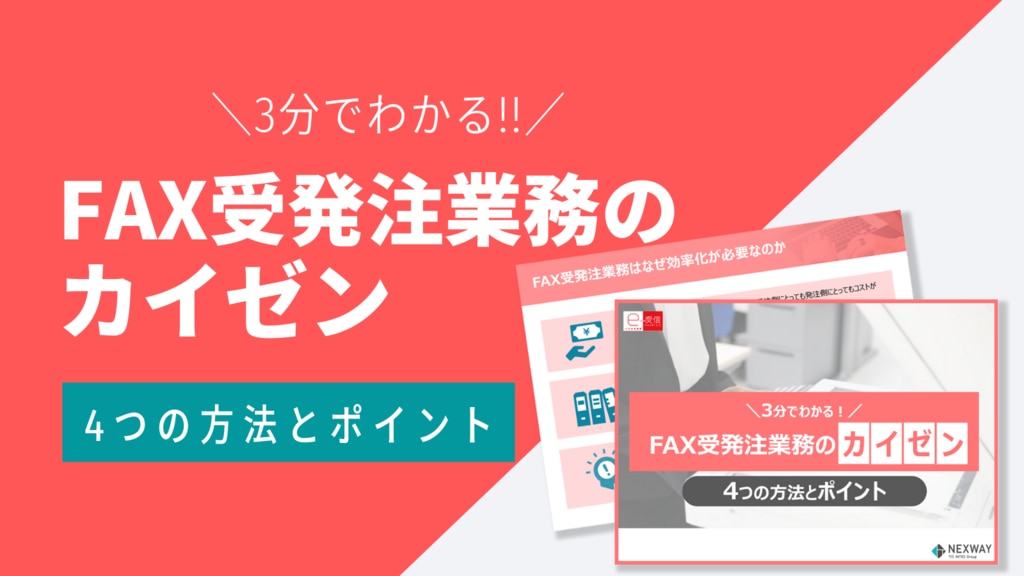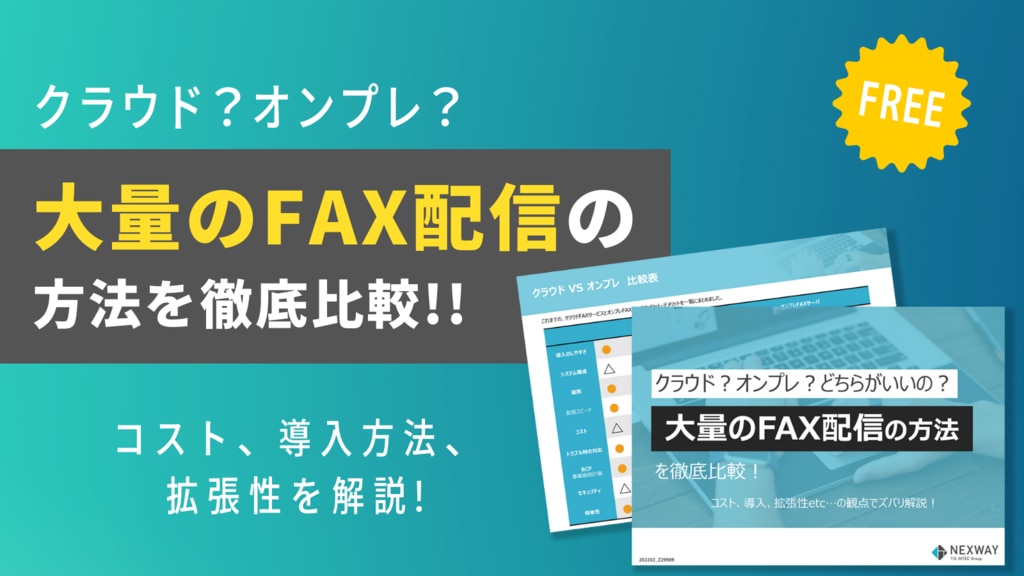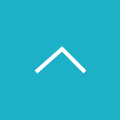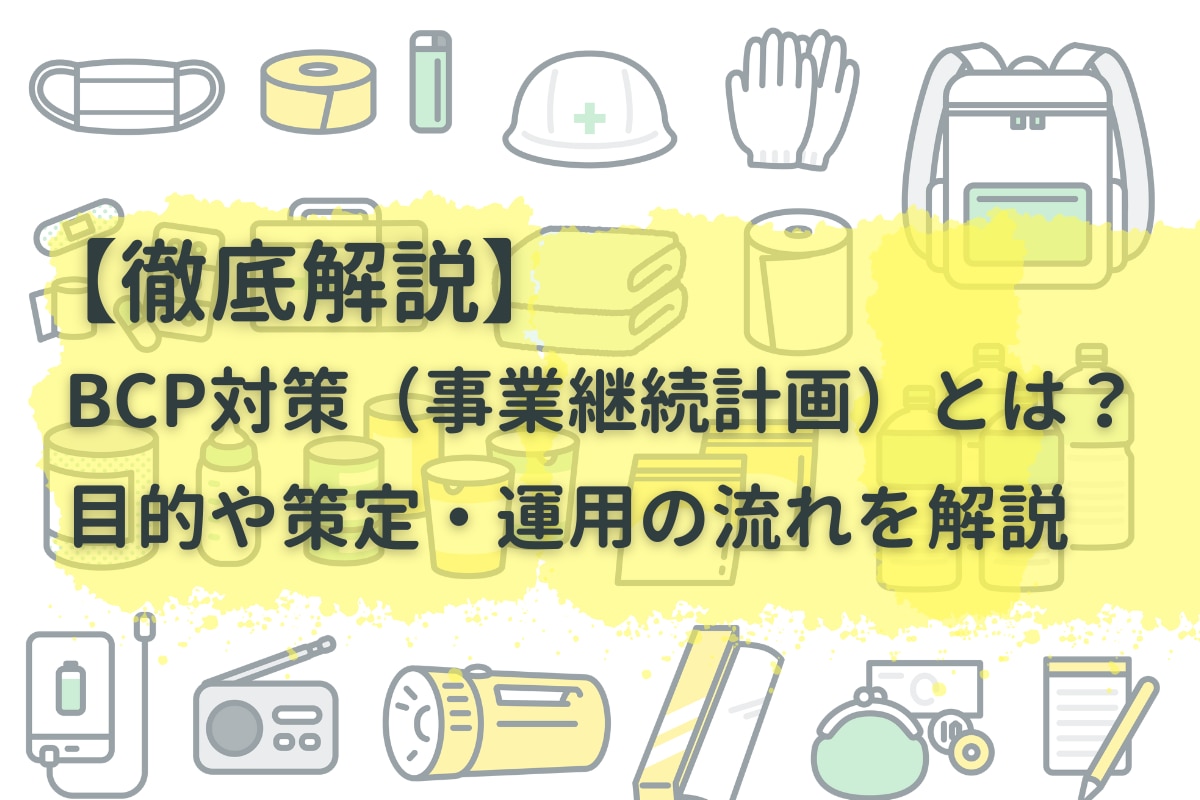
【徹底解説】BCP対策(事業継続計画)とは?目的や策定・運用の流れを解説
「受信したFAXのデータ化でお悩みですか?」
クラウドFAXをAI-OCRと連携して受注業務の完全ペーパーレス化
[詳しくはこちらから]
目次[非表示]
- 1.BCP(事業継続計画)対策とは
- 2.BCP対策が求められる背景
- 2.1.1.自然災害の増加と大規模化
- 2.2.2.感染症リスクの顕在化
- 2.3.3.サイバー攻撃の増加と高度化
- 2.4.4.サプライチェーンの脆弱性
- 2.5.5.法規制・取引要件の強化
- 3.BCP対策と防災対策の違い
- 4.BCP対策の目的
- 4.1.従業員を守る為
- 4.2.事業を早期普及させる為
- 5.BCPとBCMの関係性
- 6.BCP対策マニュアルには3種類ある
- 6.1.自然災害向けマニュアル
- 6.2.外的要因にともなう緊急対応マニュアル
- 6.3.内的要因にともなう緊急対応マニュアル
- 7.BCP策定・運用の流れ
- 7.1.方針を決める
- 7.2.優先する事業を特定する
- 7.3.被害のシミュレーションから事前案を決める
- 7.4.計画を策定する
- 7.5.BCP発動基準や体制を整備する
- 7.6.社内へ周知し、定着させる
- 8.BCP策定の際の課題
- 8.1.形骸化して機能しない
- 8.2.コストや時間がかかる
- 8.3.社内にノウハウがなく、着手できない
- 9.BCP対策を行うメリット
- 9.1.緊急時の速やかな対応につながる
- 9.2.企業価値・信頼性を高める
- 9.3.経営戦略へつなげることができる
- 10.BCP対策におすすめのツール・サービス
- 10.1.バックアップサービス
- 10.2.安否確認システム
- 10.3.FAX受発注(クラウド型FAXサービス)
- 11.まとめ
こんにちは。「FNX e-受信FAXサービス」ライターチームです。
企業が行うべき緊急事態への備えの一環として、2007年の新潟・中越沖地震や2011年の東日本大震災を機に推進されている「BCP対策」。その策定や強化をご検討中の方のなかには、BCP対策に関する基礎知識を事前に押さえてから、導入や再検討を進めたいとお考えの方も多いでしょう。
そこでこの記事ではBCP対策の概要をご説明するとともに、そのメリットや策定・運用のおもな流れなどをご紹介します。
BCP(事業継続計画)対策とは
BCPとは「Business Continuity Plan(事業継続計画)」の略称で、災害や事故などの緊急事態が発生した場合でも、事業を継続または早期に復旧するための行動計画です。BCPの本質は「どんな状況でも重要な事業を止めない」という点にあります。
具体的には、以下の要素を含む包括的な計画となります。
自社が直面する可能性のあるリスクの特定
重要業務とその優先順位の決定
目標復旧時間(RTO)と目標復旧レベル(RLO)の設定
緊急時の体制と指揮命令系統の確立
具体的な対応手順の策定
必要な資源(人材・設備・情報など)の確保
訓練と計画の定期的な見直し
BCPは単なる災害対策ではなく、経営戦略の一環として位置づけられる重要な計画です。事業の根幹を守り、顧客や取引先との信頼関係を維持するためのものであり、企業の存続を左右する可能性さえあります。
BCP対策が求められる背景
近年、様々な要因からBCP対策の重要性が高まっています。
その背景には以下のような要素があります。
1.自然災害の増加と大規模化
日本は地震、台風、豪雨、火山噴火など自然災害が多発する国です。2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、2018年の西日本豪雨、2019年の台風19号、2023年の能登半島地震など、大規模な災害が続いています。気候変動の影響もあり、水害のリスクも高まっています。
2.感染症リスクの顕在化
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、多くの企業に事業継続の危機をもたらしました。出社制限やサプライチェーンの寸断により、事業継続が困難になった企業も少なくありません。このような感染症リスクへの備えも、現代企業には不可欠となっています。
3.サイバー攻撃の増加と高度化
デジタル化の進展に伴い、サイバー攻撃のリスクが増大しています。ランサムウェアなどによる被害は年々増加しており、システム停止による業務中断も現実的な脅威となっています。2022年には自動車部品大手のサプライヤーがサイバー攻撃を受け、自動車メーカーの生産にも影響が出る事態も発生しました。
4.サプライチェーンの脆弱性
グローバル化によりサプライチェーンは複雑化し、一部の調達先に問題が生じるだけで、生産活動全体に影響が波及するリスクが高まっています。東日本大震災や新型コロナウイルス感染症では、直接被災していない企業でも、部品調達の停滞により生産停止を余儀なくされるケースが多発しました。
5.法規制・取引要件の強化
上場企業を中心に、BCP策定が事実上の義務となりつつあります。また、大企業との取引において、BCP対策の有無が取引条件となるケースも増えています。さらに、ESG投資の観点からも、リスク管理体制の一環としてBCPの整備状況が評価対象となっています。
これらの背景から、あらゆる規模・業種の企業にとって、BCP対策は経営上の重要課題となっています。
BCP対策と防災対策の違い
BCP対策は、災害などの緊急時に備えて講じておくものです。もし、企業内で既に防災対策を実施している場合、「新たにBCP対策を実施する必要はあるのだろうか」と思うかもしれません。
しかし、BCP対策と防災対策の内容は似ているものの、目的や対象事案にはいくつか異なる部分があります。ここでは、その相違点をご紹介します。
防災対策は自然災害への備え、BCP対策はそれ以外も含む
防災対策は、大地震や大規模台風、火山の噴火といった自然災害から企業を守るための対策です。防災対策とBCP対策の両者とも、緊急時に企業を守るという基本の目的自体は変わりません。
しかしBCP対策では、防災対策で対象となっている自然災害だけではなく、火災や事件・事故、テロや感染症、社内システムのダウンや遅延など、あらゆる緊急事態を対象に含みます。
自社を守る防災対策、他社も含めて被害を防ぐBCP対策
防災対策によって実現されるのは、自然災害から自社の人材や資産を守ることです。それに対し、BCP対策では人材・資産の保護はもとより、事業を止めずに継続させることまでを目的に含んでいます。
このため、策定にあたっては取引先など関係者との共同作業を要します。場合によっては、関連する他社の資産を守ることも対策に含むでしょう。
例えば、複数の金融機関が緊急時に備え、バックアップセンターを共有する取り組みなどが具体例のひとつです。この例は緊急時対策と経費削減の両立を図れるため、備えとしてのメリットが大きいといわれています。
BCP対策の目的
BCP対策を実施するうえで特に重視すべき2つの目的、「従業員の安全確保」と「事業の早期復旧」について詳しく解説していきます。
従業員を守る為
BCP(事業継続計画)対策の最も基本的な目的は、災害や事故が発生した際に従業員の命と安全を守ることです。企業活動は人によって成り立っており、どれほど優れた設備や資産があっても、従業員が安心して働ける環境がなければ機能しません。そのため、地震や火災、感染症などの緊急事態を想定し、避難訓練の実施や安否確認システムの整備、非常食・水の備蓄といった具体的な対策を講じておくことが重要です。また、交通機関が止まるような状況に備え、テレワーク体制を整えることも、従業員の安全と業務継続の両立に貢献します。
事業を早期普及させる為
従業員の安全が確保された後に必要なのが、事業の早期復旧です。災害によってオフィスや工場が被害を受けた場合でも、業務を可能な限り速やかに再開することは、取引先や顧客からの信頼を守る上で不可欠です。具体的には、重要業務の優先順位付け、代替設備の確保、クラウドを活用したデータ管理、そして複数の調達先の確保など、平時からの準備が復旧スピードを大きく左右します。BCP対策は、単なるリスク管理ではなく、企業の競争力を維持する戦略的取り組みといえます。
BCPとBCMの関係性
BCM(Business Continuity Management:事業継続マネジメント)とは、BCPを策定・運用するための継続的なマネジメントプロセス全体を指す概念です。BCPが「計画」であるのに対し、BCMは「計画を効果的に機能させるための管理活動」と言えます。
BCMには以下のような活動が含まれます。
- BCPの策定と文書化
- 教育・訓練の計画と実施
- 計画の定期的な見直しと改善
- 組織体制の整備と維持
- 必要なリソースの確保と管理
BCMの核心は、BCPを「策定して終わり」ではなく、継続的に運用・改善し、組織文化として定着させることにあります。実効性のあるBCPを維持するためには、このBCMの視点が不可欠です。
BCP対策マニュアルには3種類ある
BCP対策の策定において、重要なのが緊急時にすべきことをまとめたマニュアルです。緊急事態が生じるおもな要因は、自然災害・外的要因・内的要因の3つに分けられるため、BCP対策マニュアルもそれらに対応すべく3つに分類する必要があります。
自然災害向けマニュアル
自然災害に対応したマニュアルを作成する際には、以下に関する内容を必ず盛り込みましょう。
- 被害状況の確かめ方
- 人命救助の手段や手引き
- 安全な場所へ避難するための手順
- 従業員の安否を確認する方法
- 事業を止める必要がある場合の代替設備・手段の活用方法
- 停電が発生した際の情報管理の手法(紙管理への切り替え方法など)
外的要因にともなう緊急対応マニュアル
火災や事故、テロなどによる緊急時においては、自然災害向けのマニュアルに記載された事項をある程度活用可能です(人命救助や被害状況確認、安否確認など)。
ただし、外的要因による緊急事態には、大口取引先の倒産・廃業やサイバー犯罪被害なども含まれるため、それらの事態への備えについても盛り込む必要があります。
仕入先や依頼先を二重化することや、万一の際の取引先変更対象となる企業リストの作成などをマニュアルに含めておきましょう。
また、サイバー攻撃による情報漏えいなどが発生した場合は、被害を受けると同時に取引先や株主などに対する説明責任を負う可能性もあります。そういった事態に見舞われることに備え、関係者へ説明すべき内容や対応の手引きをマニュアル内で決定しておくことも必要です。
内的要因にともなう緊急対応マニュアル
内的要因による緊急事態とは、おもに社内で発生した事案にともなう被害によるものです。社内事案には、従業員や関係者による情報漏えいをはじめ、企業公式SNS炎上などに代表される不祥事も含まれます。
このような事態が起こると実際の被害にとどまらず、顧客や消費者からの意見・苦情への対応に追われてさらに損失を生む可能性もあります。それらを想定し、問い合わせ窓口の増設やクレーム対応の手引きなどをマニュアル内で決定しておく必要があるでしょう。
BCP策定・運用の流れ
BCP対策を策定する際は、どのような手順を踏んで計画を立てる必要があるのでしょうか。ここでは、BCP対策を策定し運用を進めるまでのおもな流れを、検討段階から運用開始後までにわたり、くわしくご紹介します。
方針を決める
まず、自社がなぜBCP対策を策定するのか、BCP対策によってめざすものが何であるかを明確にしましょう。企業としての方針が事前にきちんとまとめられ共有されていれば、万一の事態に見舞われた際も各従業員が最適な行動を速やかにとれます。
具体的には、以下のような要点に沿って自社のBCP策定方針を決定するとよいでしょう。
- 自社において想定できる災害や大規模リスクをピックアップする
- ピックアップした各災害・リスクに自社が見舞われた場合の影響度を想定する
- 受ける影響度を踏まえ、BCPで対象とする災害やリスクの絞り込みを行う
上記を実施し、自社の経営理念や事業目的なども考慮しながら、リスクから自社を守るBCPを策定するための方針をまとめていきましょう。
優先する事業を特定する
複数の事業を行っている企業も数多くあります。そのような場合は、緊急時にどの事業の継続や復旧を優先するか事前に決めておくことも必要です。
優先する事業を決定する際は、以下のような基準を設けておくと役立ちます。
- 売上の比重の高さや利益の大きさ
- 業界内シェアの高さや企業の信用維持にともなう重要性
- 事業が止まったり遅れたりした際の損害の程度 など
どの事業を優先するか判断する場合、個々の主観や単一要件だけではなく、売上や利益、影響を受ける顧客数など多方面からの視点で検討しましょう。
被害のシミュレーションから事前案を決める
先に優先することを決定した事業について、万一の際に受ける被害の程度を想定しシミュレーションを行います。この際には必ず、自然災害・外的要因・内的要因の3つそれぞれにおける被害を想定しましょう。
それに基づき、事業が停止した際の復旧までにかかる時間の目安を算出し、復旧までの目標時間の決定など事前の対策案を詳細に決めていきます。
計画を策定する
ここまで立案した内容に沿い、具体的な計画を策定してマニュアルを作ります。マニュアル作成時は、緊急対応の過程を以下のように段階化すると、より詳細で分かりやすいマニュアルになるでしょう。
- リスクの発生とBCP発動の段階
- 被害からの復旧と並行し事業継続や早期再開を図る段階
- 障害を取り除き業務を通常化する段階
- 全面的な復旧に至る段階
上記の段階化に加え、以下の観点をつねに意識してマニュアルの作成にあたるようにしましょう。
- 人材の確保:従業員とその家族の安否を確認し最優先で人命を守る
- 施設や設備の保全:損害を受けた施設・設備の代替や復旧の推進
- 金銭的損失の補填:保険による経済的補償や公的融資などの活用
- 体制不全の補完:事業のチーム体制に支障をきたした場合の対応方法
- 情報資産の持続や復旧:損害を受けた情報機器の代替やデータバックアップなど
従来、リスク対応において重んじられてきた人命保護や設備の復旧に加え、近年は情報資産を守ることも特に重視されています。重要なデータを失ってしまうと、事業継続に大きな障壁が生じてしまうためです。
遠隔地にある拠点でのバックアップや、複数箇所でのデータの分散化を積極的に行いましょう。
BCP発動基準や体制を整備する
BCPの計画書やマニュアルを作成する際は、BCPの発動基準とBCPに沿って行動する際の体制を明確にしておかなければなりません。これらをはっきりさせないと、最適なタイミングでBCPを発動できず、本来防げたはずの損害を生んでしまうおそれがあるためです。
それに加え緊急事態下は気が動転し、個々の判断力が平時より低下してしまう可能性もあります。あらかじめチーム体制を決めておき、リーダーの指示で迅速に行動できる状況を整えましょう。特にBCP発動時に個々がとるべき行動に関して、できるだけ具体的かつ詳細に決定しておくことにより、現場での混乱回避に努めてください。
社内へ周知し、定着させる
BCP対策は、それにかかわる人たち全員が把握していなければ計画通りに機能しません。すべての従業員や関係者に向け、社内教育などでBCPが策定されたことの周知が必要です。
BCPの運用開始後は継続的な訓練を実施し、いつでも計画に沿った行動をとれる状態にしておきましょう。また先に述べたとおり、BCPは自社の資産だけを守るための取り組みではありません。顧客や取引先をはじめ、協力会社や事業所がある地域の人々などと相談し、緊急事態が起こった際の協力体制も構築しておく必要があります。
社内外にBCPを定着させるには、運用しながら社内事情や情勢変化などを鑑みて内容を見直すことも欠かせません。運用→見直し→改善→再運用のサイクルを繰り返し、つねに最新かつ最適なBCP対策の運用に努めてください。
BCP策定の際の課題
企業がBCP(事業継続計画)を策定しようとした際、多くの現場では「必要性は理解しているが、なかなか実行に移せない」という課題に直面します。その背景には、現実的な運用面での障壁がいくつも存在しており、計画そのものが機能不全に陥るケースも少なくありません。ここでは、BCP策定時によく挙がる3つの代表的な課題について解説します。
形骸化して機能しない
BCPが「策定しただけ」で終わってしまうケースは珍しくありません。とりあえず文書を整備したものの、現場の実態と乖離していたり、定期的な見直しや訓練が行われなかったりすることで、いざという時に何の役にも立たないという状況が生まれます。特に組織の変化や人事異動によってBCPの管理者が不明確になった場合、計画は棚上げ状態となり、形式だけが残ってしまいます。BCPが形骸化しないようにするためには、定期的な見直しと訓練を実施し、組織の変化や人事異動に対応できる柔軟な管理体制を構築することが重要です。計画の実効性を高めるため、明確な責任者を設定し、実際の業務に即した内容に更新し続けることが求められます。
コストや時間がかかる
BCPの策定や訓練には、一定のコストと工数が伴います。リスク分析や業務の優先順位付け、復旧プロセスの設計などは専門的な知識を要し、関係各所の調整や資料作成にも多くの時間を要します。そのため、目の前の業務に追われている企業では、後回しにされることが多く、「投資対効果が見えにくい」として経営層の理解を得るのも一苦労です。そのため、BCPの策定が企業の継続的な成長とリスク軽減にどれだけ重要かを具体的なデータや事例を用いて説明し、投資対効果を明確に示すことが求められます。
社内にノウハウがなく、着手できない
特に中小企業では、BCPをどこから手をつけてよいか分からないという悩みもよく聞かれます。専門部署がない、情報収集の手段がない、他社事例を知る機会がないといった理由から、BCPが必要だと分かっていても実際に動き出せないのです。結果として「何かあったらそのとき考える」という属人的な対応に頼りがちになり、組織としての危機対応力が育たないという悪循環に陥ります。BCPに着手できない問題を解決するためには、まず専門的なサポートを外部に依頼したり、オンラインリソースや業界事例を活用したりすることで、情報収集を始めることが重要です。また、段階的に取り組むことで、少しずつ組織としての危機対応力を高め、実行可能な計画を作成していくことが求められます。
BCP対策を行うメリット
BCP対策を実施する具体的なメリットには、どのようなことが挙げられるのでしょうか。ここでは、BCP対策を行うメリットをご紹介します。
緊急時の速やかな対応につながる
緊急事態が起こった際に最優先されるのは、当事者の命を守ることです。BCP対策が適切に策定されており、すべての関係者がそれに沿って迅速に正しく行動できれば、まず人命にかかわる被害を防げるでしょう。
それらの行動で人材が守られることにより、事業の継続や早期復旧の実現にもつながります。
企業価値・信頼性を高める
BCP対策がきちんと策定・運用されていることで、不測の事態においても適切に行動でき、途切れることなく製品やサービスの提供を行える優良な企業とみなされます。取引先や地域住民からの信頼も得られ、企業の印象を高めることにもつながるでしょう。BCP対策が整えられていることは、ひいては企業自体の信頼性や価値の向上にも寄与するといえます。
経営戦略へつなげることができる
BCPを策定する段階では必ず、優先する事業の絞り込みや復旧を進める上での段階的措置について検討することとなります。この取り組みによって、自社にとってどのような業務が重要であるかの再確認にもつながるでしょう。
基幹事業がどの業務で、どの業務の重要性が低いかについて改めて認識できることで、経営戦略の見直しへと役立てることも可能です。
BCP対策におすすめのツール・サービス
BCP対策は計画書やマニュアルを作ることだけではなく、計画を運用するため新たにツールやサービスを導入し活用することもその一環です。ここでは、BCP対策としての導入が推奨されるツールやサービスについてご紹介します。
バックアップサービス
重要な情報が含まれたデータを災害や有事で失わないため、外部や遠隔地へのバックアップを行うことはBCP対策においても重要です。BCP対策に対応した外部によるバックアップサービスも数多く展開されていますので、それらを利用し情報関連の緊急時対応をアウトソーシングする方法もひとつの手でしょう。
安否確認システム
緊急時に従業員やその家族の状況を早期に確認するためには、安否確認システムの活用が欠かせません。しかし、安否確認システムの複雑な仕組みや仕様を、社内で一から構築することは容易ではないでしょう。外部の安否確認システムを導入し、いつでも確実に人員の動向を把握できる状態を整えておくとよいでしょう。
FAX受発注(クラウド型FAXサービス)
FAXで受発注業務を行っている企業において、緊急事態によりFAX機能を損なってしまうことは重大な障害です。拠点への出社ができない状況でもFAX受発注業務を停止させないため、クラウド型FAXサービスの導入をご検討ください。
クラウド型FAXサービスとは、インターネット接続可能な環境とPCが用意できれば、いつどこにいても受信したFAXの確認と返信を行えるサービスです。取引先・拠点間でやり取りするFAXのデータはクラウドサーバ上にすべて保管され、自宅や外出先からFAXの記録と内容を確認可能。
万が一、ある拠点への出社ができなくなっても、他の拠点からその拠点宛に届いたFAXをカンタンに確認できます。
オフィス内のFAX機器をチェックするためだけの出社も不要になるため、災害対策などにとどまらず、働き方改革にともなうテレワーク推進にも役立つでしょう。
まとめ
企業がBCP対策を策定・運用することで、災害や大規模システム障害などの緊急時においても適切な行動で人命や資産を保護できます。これにより事業だけではなく、働く人たちの生活も止めず守ることにつながるでしょう。
BCPの適正な運用には最新のマニュアルや人員体制の整備とともに、BCPに対応できる業務環境を準備しておくことも重要です。特にFAXで受発注を行っている企業では、「もし災害でFAXが止まったら……」と危機感を覚えているかもしれません。
ネクスウェイでは、今使用中のFAX番号をそのまま使用できるクラウド型FAXサービス「FNX e-受信FAXサービス」をご提供しています。FAX受発注業務のBCP対応でお悩みをお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。