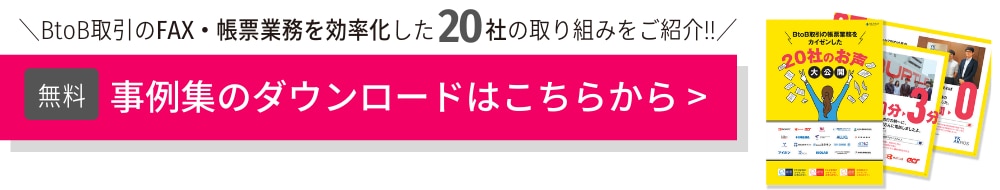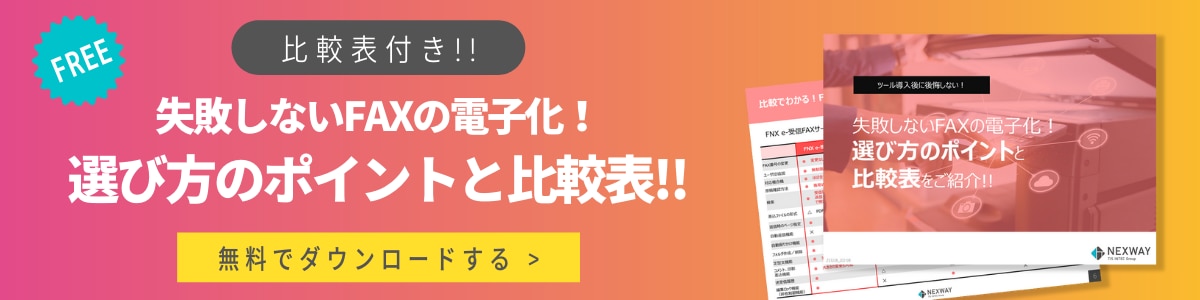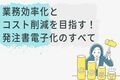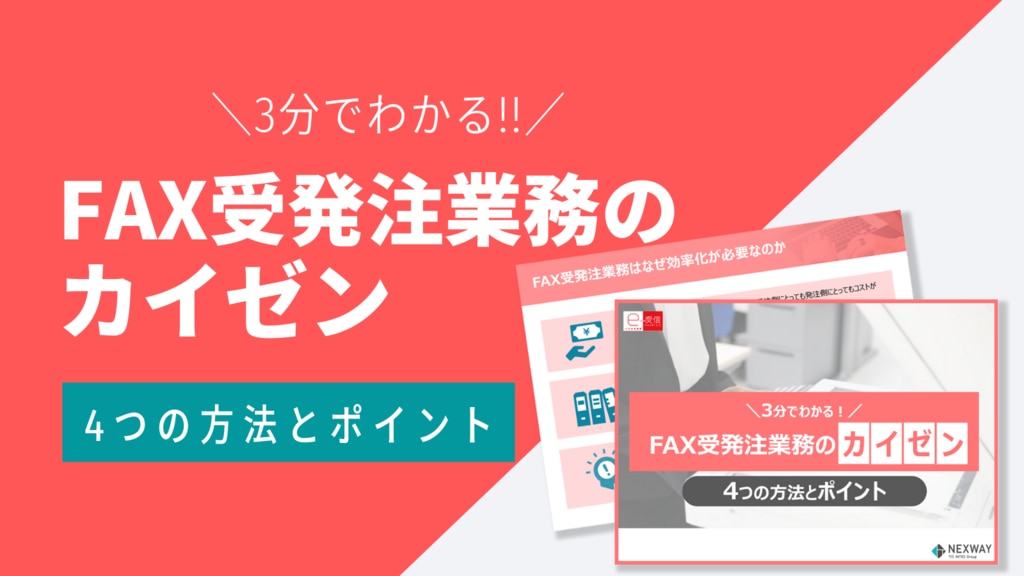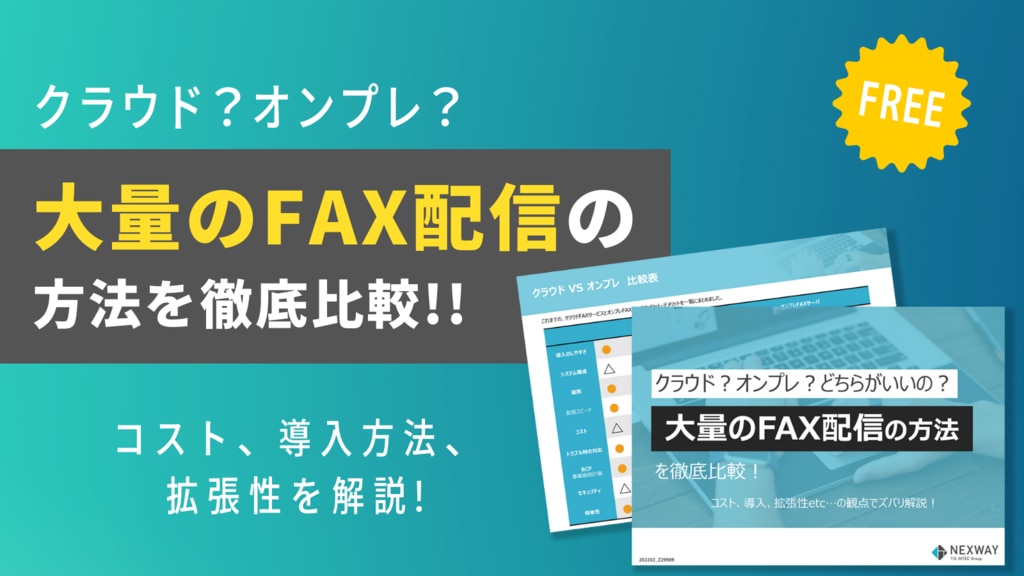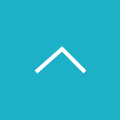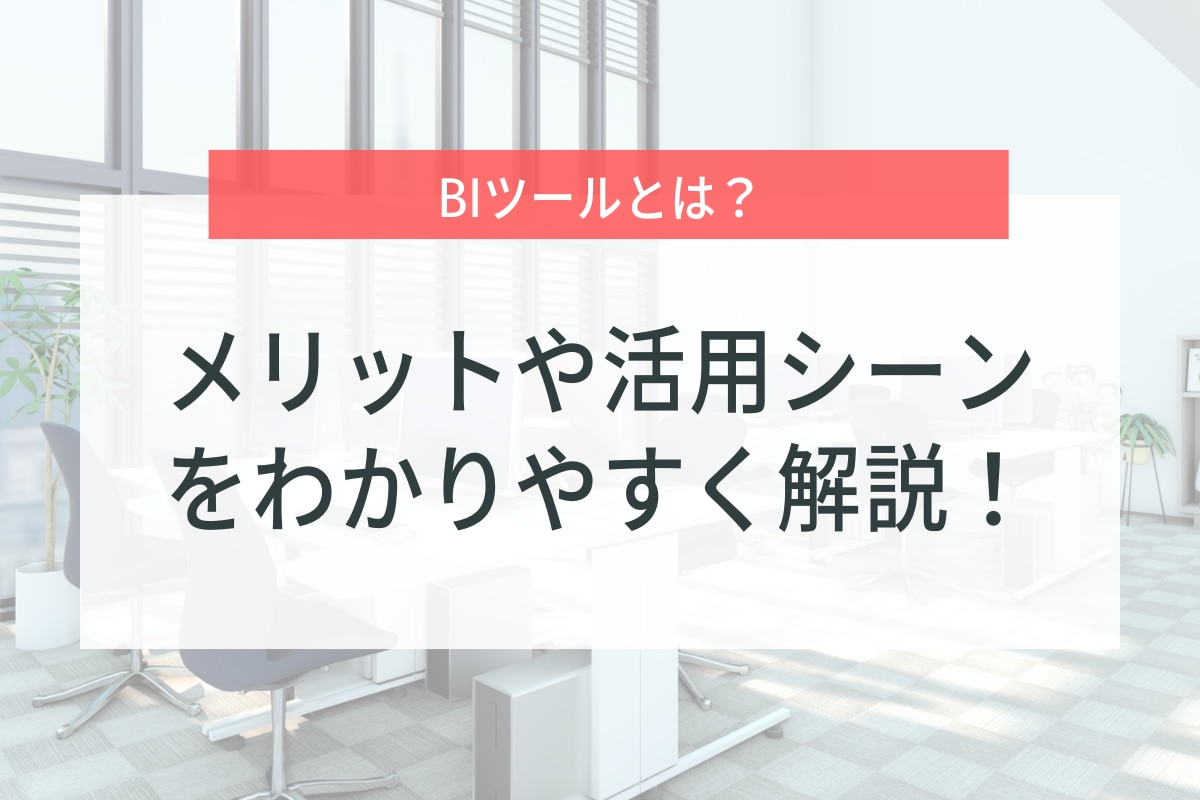
BIツールとは?メリットや活用シーンをわかりやすく解説!
「BIツール(Business Intelligenceツール)」とは、企業や組織が蓄積しているデータを収集・分析し、経営や業務上の意思決定に役立つ情報を可視化・提供するソフトウェアの総称です。
企業活動では、売上や在庫、顧客属性、購買履歴、製造工程の稼働状況、経理・財務データ、Webアクセス解析やSNSでの反応など、多種多様なデータが日々生み出されています。
しかし、これらのデータが縦割りに管理され、組織全体で十分に活用されていないケースも少なくありません。
そこで、そうした課題を解決し、データを迅速かつ的確な意思決定に生かすためのソリューションとして注目を集めているのが「BIツール(Business Intelligenceツール)」です。BIツールを導入すると、複数のシステムやスプレッドシートに分散している情報を一元的に取り込み、リアルタイムに可視化・分析できるようになります。
目次[非表示]
- 1.BIツール導入のメリット
- 1.1.社内のデータ活用レベル向上
- 1.2.業務効率化と意思決定の迅速化
- 1.3.部署間でのKPI共有による経営の透明性向上
- 2.BIツールでできること
- 3.BIツールが活用されるシーン
- 3.1.経営層の場合
- 3.2.マーケティング担当者の場合
- 3.3.IT部門でのDX推進者の場合
- 3.4.事務・経理担当者の場合
- 4.BIツール導入のデメリット
- 4.1.コストの問題
- 4.2.運用体制の整備
- 4.3.データ品質・整合性の問題
- 4.4.導入初期の定着化までのハードル
- 5.BIツールの種類
- 5.1.オンプレミス型
- 5.2.クラウド型(SaaS型)
- 6.BIツールの選び方
- 6.1. ステップ①自社の課題と目的を明確化する
- 6.2.ステップ②導入形態(オンプレミス or クラウド)を検討する
- 6.3. ステップ③コストとROI(投資対効果)を試算する
- 6.4.ステップ④操作性・UI/UXをチェックする
- 6.5.ステップ⑤拡張性や連携性を考慮する
- 6.6.ステップ⑥スモールスタートと段階的拡張を意識する
- 7.受注業務効率化のおすすめツール
BIツール導入のメリット
なんとなくBIツールがどんなものかイメージしていただけましたでしょうか。イメージが湧いた方もそうではない方もBIツールにどんなメリットがあるのか?BIツールで何ができるのか?気になるのではないでしょうか。
そんな読者の皆様にここからはBIツール導入のメリットとBIツールでできることをご説明します。
社内のデータ活用レベル向上
BIツールを使うことで、組織全体に「データを使って考える」文化が根付きやすくなります。これまでExcelや紙を中心に業務を行っていた方でも、見やすいグラフや簡単な分析機能を通じて、数字に基づいたアイデア出しが可能になるため、データをもとに考えることが習慣化されやすいのです。
業務効率化と意思決定の迅速化
2つ目のメリットは業務の工数削減による業務効率化と意思決定の迅速化です。もともと手動で行っていた業務を自動化することができ、担当者の方は付加価値の高い仕事に時間を割けるようになります。
また、データのリアルタイム更新を実現することで、意思決定のタイムラグを短縮することも可能です。意思決定までのタイムラグを抑えることで、ビジネスチャンスを逃さない企業運営をBIツールがサポートしてくれます。
部署間でのKPI共有による経営の透明性向上
部署ごとに異なる指標を管理していると、どこが何を目標としているのか分かりづらい状態に陥りがちです。BIツールを導入し、全社共通のダッシュボードを用意すれば、会社全体で同じ指標を見ながら目標に向かうことができます。
これにより、いまどの部署がどの程度目標に近いのか、あるいは何がボトルネックになっているのかを全員が把握しやすくなり、経営の透明性が高まるだけでなく、コミュニケーションや部署間連携もスムーズになります。
BIツールでできること
BIツールの最大の特徴は、大規模データを効率よく処理し、全社共通の「正しい情報」を参照できる環境を整えられる点です。Excelや手作業で集計する場合、扱いきれないほどのデータ量やファイル管理の煩雑さが問題になることがあります。
しかし、BIツールであれば、これらの問題を解消しつつ、情報を集中管理することができます。以下では、BIツールでどんなことができるのか?ご紹介します。
リアルタイムなデータ収集・統合
BIツールの重要な機能の一つに、社内システムや外部サービスと連携し、リアルタイムもしくは定期的にデータを収集・統合できる仕組みがあります。
これにより、部署ごとにデータがバラバラに存在して「どれが最新なのか分からない」といった混乱が減少します。さらに、自動でデータを取り込み、更新してくれるため、Excelの巨大なファイルを複数人で受け渡しする必要がなくなります。
データの可視化・ダッシュボード作成
BIツールでできることの2つ目は、多種多様なグラフやチャートを使って、データを分かりやすく“見える化”することです。棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、ゲージチャート、ヒートマップ、ツリーマップなど、分析目的やデータの特性に合わせて自由に形式を選択することができます。
また、「ダッシュボード」と呼ばれる画面に複数のグラフや指標をレイアウトしてまとめておけば、重要なKPIを一目で把握することもできます。
たとえば経営層向けには会社全体の売上や利益を、現場担当者向けには特定の商品や顧客にフォーカスした情報を、マーケティング担当者向けには広告ROIやキャンペーン効果を表示するなど、用途に応じて複数のダッシュボードを作成することができます。
分析機能(ドリルダウン・シミュレーションなど)
BIツールでは、データの可視化だけでなく、深掘り分析をサポートする高度な機能を備えている場合が多いです。代表的なものが「ドリルダウン分析」です。
ドリルダウン分析とは、上位レベルの集計データから地域別・商品別・担当者別など詳細レベルのデータへ掘り下げる分析方法です。ドリルダウン分析の機能を活用することで、会議中に「この数字の内訳はどうなっているのか?」と疑問を持ったときでも、その場で確認が可能です。
さらに、「What-if分析」や「シミュレーション機能」を搭載したBIツールでは、価格や宣伝費などの変動が売上や利益に与える影響を瞬時に試算することができます。
Excelでも同様の分析はできますが、BIツールを使うと大量データや複雑な前提条件に対しても柔軟に対応できるため、複数のシナリオを比較する経営層や管理職にとっても嬉しい機能であると考えます。
レポート作成の自動化
企業には、定例ミーティングや経営会議、取引先への報告などで必要になるレポートが数多く存在します。多くの担当者の方が複数のExcelファイルを開き、手動でグラフを更新し、PDF化してメール送信するといった作業を週次・月次で繰り返しているのではないでしょうか。
しかし、BIツールにはレポートを自動で生成し、スケジュールに合わせて自動的に送付する機能が備わっているものが多いです。
こうした機能を使えば、最新データの取り込みからレポート生成、関係者への配信までを一括で実行できるため、単純作業を大幅に削減できます。
さらに、ダッシュボードを共有しておけば、最新データをリアルタイムで参照しながら意思決定できるので、情報伝達のスピードも向上します。
BIツールが活用されるシーン
ここからは担当業務に応じてより具体的なBIツールの活用シーンをご紹介します。
経営層の場合
まずは経営層の方のBIツール活用についてお伝えします。
リアルタイムな経営指標モニタリング
経営者や役員層にとって大切なのは、売上や利益率、キャッシュフロー、在庫回転率などの指標を、いかに早く正確に把握できるかという点です。
BIツールを使えば、各システムから取り込んだデータをリアルタイムにダッシュボードへ反映できるため、月末の締めを待たなくても日々の動向を素早く把握できます。
- 具体例
- 毎朝の役員会議前に、前日の売上実績・在庫状況・広告費などの指標をワンクリックでチェックし、必要に応じて在庫補充やマーケティング施策を見直す
全社的なKPI共有による目標達成の促進
BIツールによって、経営の重要指標を一元管理すると、社長や各事業部長、現場リーダーまですべての関係者が同じ数字をリアルタイムに確認できます。
組織全体で「どの目標(KPI)をどのレベルまで達成しているのか」が透明性高く把握できるため、施策の優先順位を柔軟に変えやすくなります。
- 具体例
- 新商品と既存商品の売上構成比を同一ダッシュボードで確認し、目標未達の場合にプロモーションや営業トークを即座に見直す
マーケティング担当者の場合
次にマーケティング担当者の方のBIツール活用についてお伝えします。
キャンペーン効果測定やターゲティングの最適化
マーケティング活動では、Web広告やメールマガジン、SNS、展示会など、さまざまなチャネルを同時に運用します。
BIツールがあれば、各チャネルのデータを自動収集し、まとめてダッシュボードに表示できるため、広告費やクリック数、コンバージョン率などを一元管理することができます。
- 具体例
- Google AdsやFacebook広告のクリック単価とECサイトの売上データを連携し、キャンペーンごとのROIをリアルタイムに監視。成果の高いキャンペーンに予算を追加配分する
また、BIツールのフィルタ機能やドリルダウン分析を利用すれば、顧客属性ごとの購買行動や継続率を瞬時に把握でき、リピート率の高い顧客や、購入単価が大きい顧客を見つけやすくなります。
- 具体例
- 20代女性顧客の購買データを分析して、特定ブランド商品の購入頻度が高いことを特定。そのブランドの商品セット割引やクーポン配信を強化して売上を伸ばす
IT部門でのDX推進者の場合
IT部門でのDX推進者向けのBIツール活用についてもお伝えします。
セキュリティ対策やアクセス制御
DX推進者は、単にツールを導入するだけでなく、機密情報の保護やアクセス権限の管理、運用ルールなどにも気を配る必要があります。
BIツールの多くには、ユーザーごとのアクセス制限やログ監査の機能が備わっているため、これらを正しく設定すれば、機密情報を守りながら全社でデータ活用を進めることができます。
- 具体例
- 営業部門には詳細な売上データを見せる一方、経理や人事データには管理職だけがアクセス可能に設定する
- 監査ログを定期的に確認し、セキュリティを強化する
事務・経理担当者の場合
最後に事務・経理担当者の方のBIツール活用についてご説明します。
不正検知
大量の会計データや請求処理には、ヒューマンエラーや不正が混ざるリスクがあります。
BIツールの異常値検知やアラート機能を活用すれば、通常とは異なる取引金額やタイミングをリアルタイムで把握でき、早期の対処が可能です。
- 具体例
- 過去の取引実績と比べて一定金額を超える請求書が届いたらアラートを出す。
- 相手先口座が急に変更された場合などもチェックする
FAX業務のデジタル化・ペーパーレス化
事務・経理の現場では、いまだにFAXで受発注伝票や請求書を受け取るケースが多く、紙作業が負担になることがあります。
BIツールと組み合わせてFAXを電子化すれば、紙書類を削減しつつ、受注や請求データを素早く分析可能になります。
- 具体例
- FAXの受信と同時にPDF化してOCR(文字認識機能)を使い、請求書番号や金額を自動抽出。BIツールのダッシュボードで未処理FAXや異常値をリアルタイムで確認する
BIツール導入のデメリット
ここまではBIツールのメリット「できること・活用シーン」をお伝えしてきました。メリットが多くある一方で、事前に理解しておくと良い注意点もあるため、ここではデメリットについてご説明します。
コストの問題
BIツールを導入・運用するには、どうしてもある程度の費用が必要です。
オンプレミス型の場合は自社サーバーの準備や保守管理費用が、クラウド型(SaaS型)でも月額やライセンス費用、利用人数が増えるときの追加料金などが発生します。
また、導入時のシステム連携やコンサルティング費用、社員向けのトレーニング費用も考慮する必要があります。
「どれくらいの投資で、どの程度の効果が見込めるか」を事前にシミュレーションし、無理のない導入計画を立てることが重要です。
運用体制の整備
BIツールを入れただけでは、その効果を最大限に引き出せません。
日々の運用やデータ更新の管理を誰が行うのか、どのような権限設定が必要かなど、運用体制をしっかりと整える必要があります。
特に多くの部署やユーザーが利用する場合、アクセス権やセキュリティ、バージョン管理なども含めてルールを明確にしておかなければ、データが更新されないまま放置されるなどのリスクがあります。
データ品質・整合性の問題
優れたBIツールでも、元となるデータが重複や誤入力などで正しく整備されていなければ、分析結果も誤ったものになってしまいます。
導入前にはデータクレンジングやマスタ整備を行い、データガバナンス(管理ルール)を確立しておくことが大切です。
こうした土台がしっかりしていれば、BIツールを使った分析も正確かつ信頼性の高いものにできると考えます。
導入初期の定着化までのハードル
新しいツールを導入するときには、社員の方が操作方法を学ぶ必要があります。Excelに慣れている現場では最初の抵抗感も大きいかもしれません。
また、導入後もビジネス環境に合わせてダッシュボードや分析指標を見直していく作業が必要です。
このため、定期的なアップデートや、BIツールのメリットを感じられる事例の共有を行い、導入初期をサポートする体制が求められます。
上からの指示だけでなく、現場の声を取り入れながら改善を続けることで、BIツールの定着度は大きく向上します。
\製造業DXの第一歩!FAX受信を電子化するなら/
失敗しないFAXの電子化!選び方のポイント&比較表ダウンロード【無料】はこちら
BIツールの種類
→ここまででBIツールの基礎については理解を深めていただけましたでしょうか。 ここからはBIツールの種類についてご説明します。
オンプレミス型
オンプレミス型とは、企業が自社サーバーにBIツールをインストールして利用する形態です。社内ネットワーク上にシステムを導入し、データも自社内に保管するため、「社外にデータを出したくない」「セキュリティ要件が厳しい」といった企業でも安心して使えます。
また、カスタマイズ性が高く、大規模データや業界特有の要件に柔軟に対応しやすいのが特徴です。
ただし、サーバーの用意やメンテナンス、システム保守などにかかるコストや手間は無視できないため、導入前に十分な検討が必要です。
クラウド型(SaaS型)
クラウド型(SaaS型)のBIツールは、ベンダーが用意したシステムをインターネット経由で使う形態です。
ユーザーは月額・年額の利用料金を支払うことで、ウェブブラウザや専用アプリからアクセスします。サーバーの準備が不要で、設定も比較的簡単なため、導入スピードが速いのがメリットです。
また、システムの運用や保守、バージョンアップをベンダー側が行うため、自社のIT部門の負担が減るという利点もあります。
ただし、クラウド上にデータを置くことになるため、セキュリティポリシーとの整合性を確認する必要があります。
大量のデータや細かいカスタマイズが必要な場合は、機能や拡張性が制限される可能性もあるのであわせて注意が必要です。
BIツールの選び方
大きくわけて2種類のBIツールが存在していることをご理解いただいた上で、この章では、BIツールの選び方について解説します。世の中にはたくさんのBIツールが存在しているため、自社にあったツール選びが重要です。
ステップ①自社の課題と目的を明確化する
「なぜBIツールが必要なのか」「どんな課題を解決したいのか」を明確化させましょう。
たとえば、
- 経営層がリアルタイムで売上やコストを把握したい
- マーケティング担当がキャンペーンのROIを瞬時に算出したい
- 事務・経理部門がレポート作成を自動化したい
などの目的が整理できれば、必要な分析機能や連携すべきデータソースも明確になります。
ステップ②導入形態(オンプレミス or クラウド)を検討する
セキュリティ要件、コスト、運用リソースなどを考慮しながら、オンプレミス型かクラウド型かを選びましょう。
- セキュリティが最優先
- 金融や医療など外部クラウドに制限がある業種はオンプレミス型を選ぶケースが多い
- スピード導入&初期コスト抑制:クラウド型(SaaS型)が向いている
ステップ③コストとROI(投資対効果)を試算する
BIツールには、ライセンス費用のほか、導入コンサル費やトレーニング費、カスタマイズ費用などの初期投資が発生します。運用中は、ライセンス更新費やユーザー数増加による追加料金もかかることがあります。
長期的にどのくらい効果が出るか(レポート作成工数の削減、人件費削減、意思決定の迅速化による収益向上など)を大まかに試算し、投資が妥当か検討しましょう。
ステップ④操作性・UI/UXをチェックする
BIツールを実際に使うのは現場の担当者であることが多いため、操作が複雑だと定着しにくくなります。
トライアルやデモ版を使って操作感を確かめる
社員が直感的に扱えそうか、研修がどれくらい必要になるか
日本語マニュアルやサポート体制の有無
これらを確認しておくと、導入後のトラブルの削減につながります。
ステップ⑤拡張性や連携性を考慮する
BIツールは、会計ソフトやCRM、MAツールなど他システムと連携してこそ威力を発揮します。将来的な業務拡大やデータ量の増大を見越し、API連携やETL機能などの拡張性をチェックしておきましょう。
ステップ⑥スモールスタートと段階的拡張を意識する
いきなり全社導入を目指すと、コストや手間が膨大になり、うまく軌道に乗らないリスクがあります。まずは特定の部署やプロジェクトで試験導入し、成功事例を積み重ねてから社内全体へ展開していくほうが、安全かつ効率的です。
ここで紹介した①~⑥のステップを参考に、自社にあったツールを検討してみてください。
受注業務効率化のおすすめツール
最後に、FAXで受信した注文書、見積書などの受注業務における各種帳票を電子化して煩雑な受注業務をサポートする「FNX e-受信FAXサービス」をご紹介します。
「FNX e-受信FAXサービス」は、既存のFAX番号をそのまま使いながら、PCから簡単にFAXの仕分け・閲覧・検索・編集・返信ができる環境を実現します。
取引先との商習慣は大きく変わらないので、DX推進への周辺の抵抗感は極めて低い特長があります。
受信したFAXをクラウド上で管理するため、紙の書類を保管するスペースがいらなくなり、紛失リスクの心配も軽減、担当者は自席から移動せずにFAXを確認できるので、業務効率が格段に上がります。
実際に、年間24,000枚ものFAXをクラウド化した企業では、約97%の工数削減を実現しました。
詳しい事例や効果を知りたい方は、下記のページをチェックしてみてください。
FAX業務のデジタル化は、BIツールとの連携を視野に入れることで、さらに大きな効果を生み出します。紙の書類を電子データに変換し、そのまま分析に活用する体制を整えれば、データドリブン経営に一歩近づけるでしょう。
ぜひ、こうしたクラウドサービスを活用して、業務効率化と生産性向上を目指してみてください。
DX化を推進中の企業様で、さまざまな仕組みの電子化ができたが、どうしてもFAXだけが紙の業務のまま残ってしまっていて現場の業務負担が大きく、「受信するFAXの仕分け、管理が大変」というお悩みをお持ちなら、ぜひ『FNX e-受信FAXサービス』までお気軽にご相談ください。