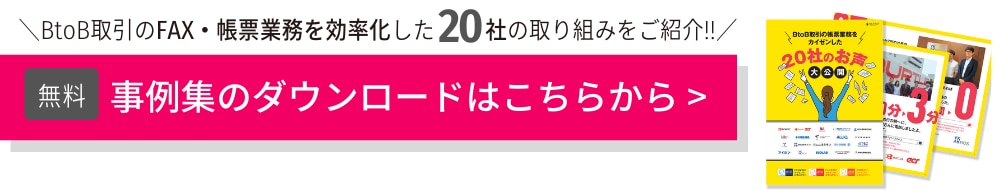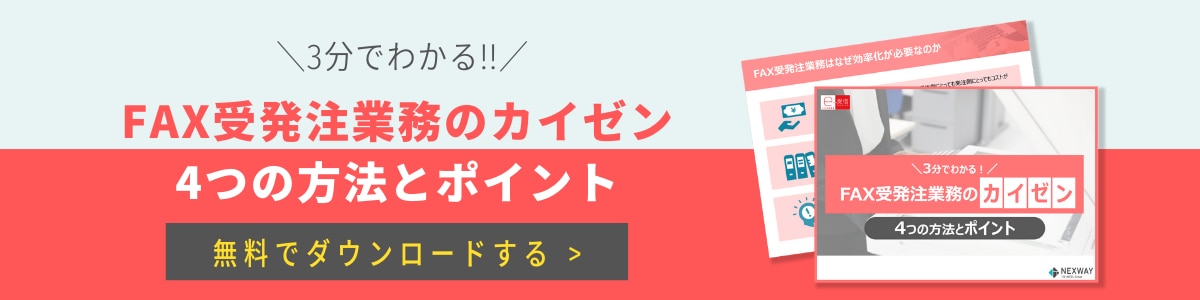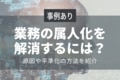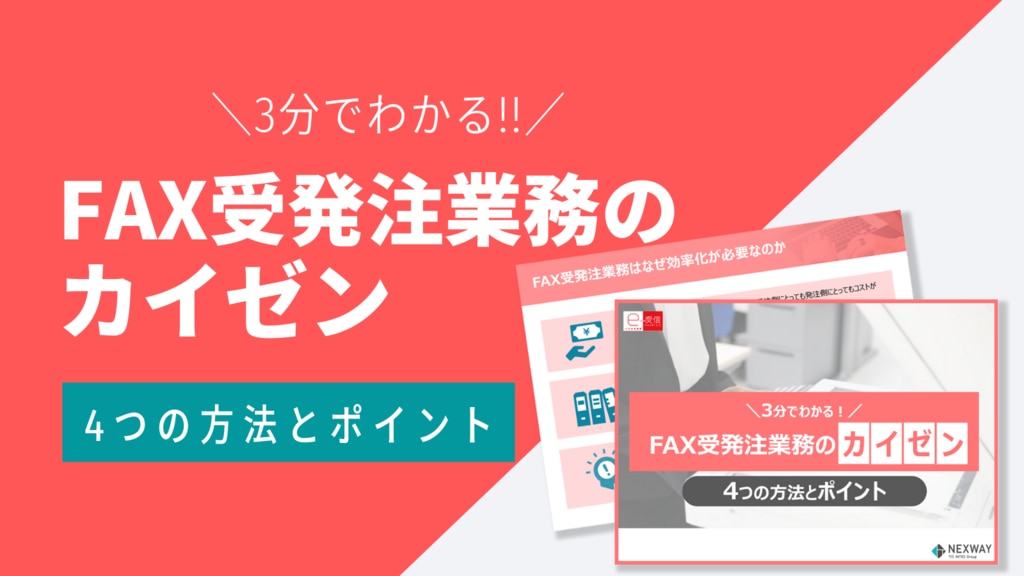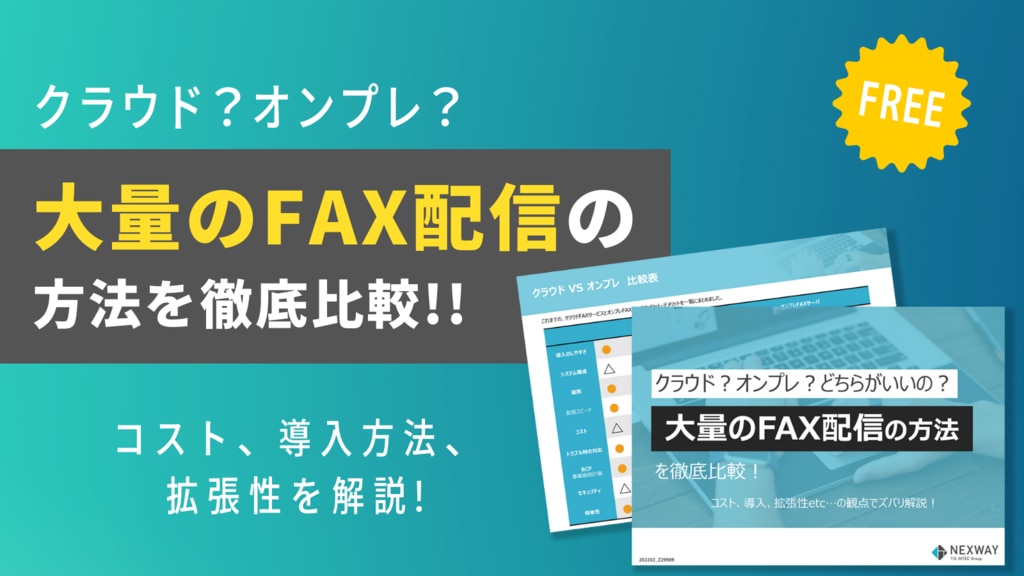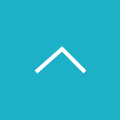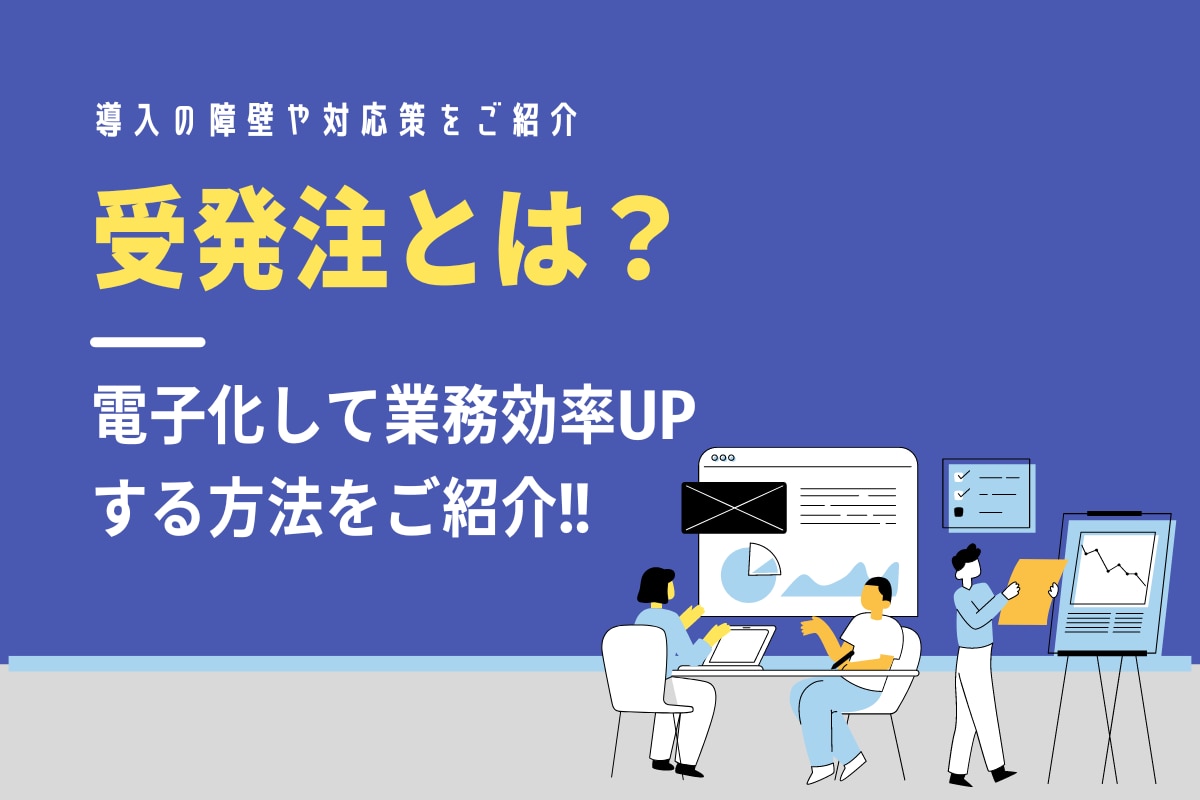
受発注業務とは?基本的な流れから課題解決の方法までわかりやすく解説します
\FAX受発注業務の効率化ができる!/
「e-受信FAXサービス」の資料を無料でダウンロードする
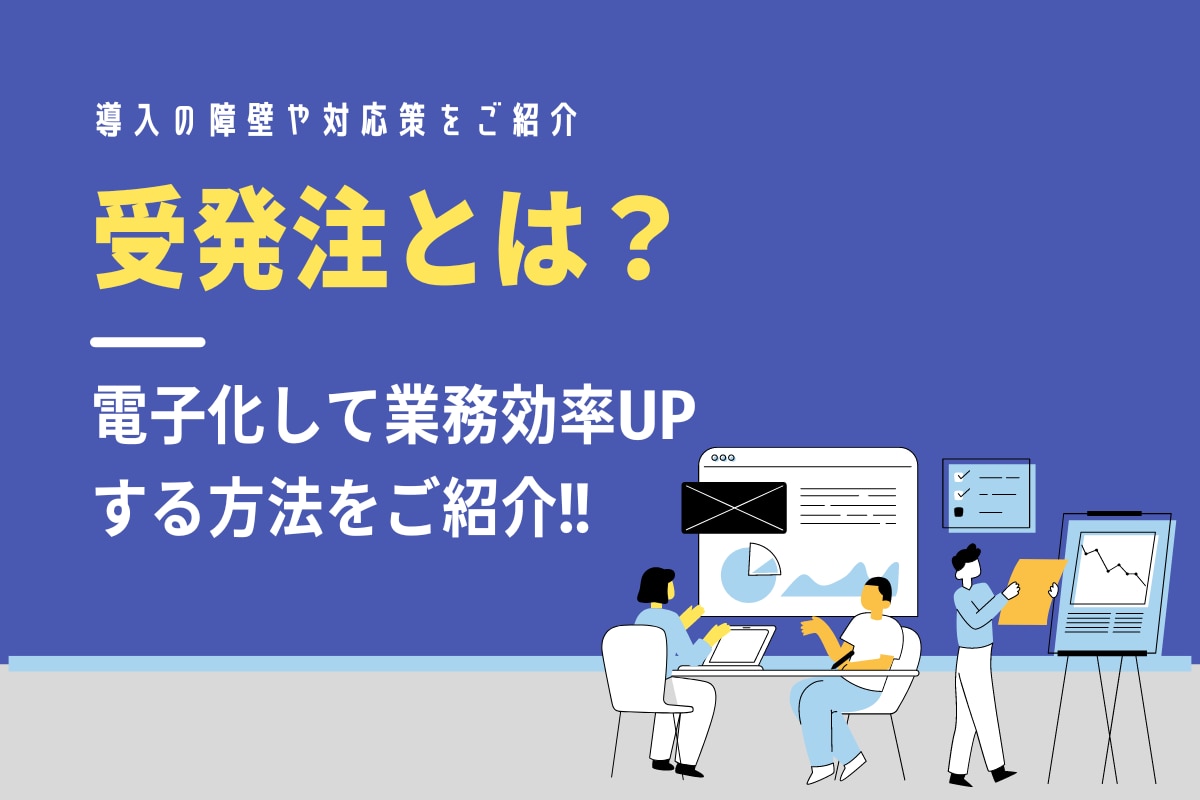
こんにちは。「FNX e-受信FAXサービス」ライターチームです。
働き方改革の推進やペーパーレス化の重要性が叫ばれている現在も、FAXによる受発注を続けている現場は少なくありません。取引先への受発注業務を効率化することは可能なのでしょうか?
この記事では受発注を効率化する方法やメリット、電子化するにあたっての障壁や対応策をご紹介します。
FAXによる受発注業務にお困りの担当者さまはぜひご一読ください。
目次[非表示]
- 1.受発注とは?
- 2.受発注の流れ
- 3.受発注業務の基本的な流れを4ステップで解説
- 3.1.ステップ1:見積もりの依頼と提出
- 3.2.ステップ2:注文の確定と契約締結
- 3.3.ステップ3:商品の発送と受領
- 3.4.ステップ4:請求と支払い
- 4.従来のアナログな受発注業務が抱える4つの課題
- 5.受発注業務を効率化するポイント
- 5.1.業務フローを可視化し、課題を洗い出す
- 5.2.システムを見直す
- 5.3.アウトソーシングやBPOを活用する
- 6.受発注システムで実現できることとは?
- 6.1.メリット1:業務自動化による効率向上とミス削減
- 6.2.メリット2:情報の一元管理とリアルタイム共有
- 6.3.メリット3:ペーパーレス化によるコスト削減
- 6.4.メリット4:取引先との連携強化と満足度向上
- 7.受発注システムを選ぶ際の比較ポイント
- 8.受発注を電子化するためのシステム「EDI」
- 9.受発注業務の電子化を妨げる要因
- 10.受発注の電子化におすすめなサービス
- 10.1.①FAX、WEB画面などが併用できるEDIサービス
- 10.2.②OCR・RPA
- 10.3.③FAX電子化サービス
- 11.まとめ
受発注とは?
受発注業務とは、顧客から注文を受け、商品やサービス提供する一連の業務の総称です。自社が提供する商品やサービスの注文を受ける「受注業務」、そして相手先企業から提供される商品やサービスを注文する「発注業務」に分けられます。
受発注の流れ
受発注業務の基本的なフローは以下の通りです。
それぞれの具体的なフローは、以下の記事で解説していますのでご覧ください。
受発注業務の基本的な流れを4ステップで解説
受発注業務は、一般的に4つのステップで進行します。発注側と受注側、それぞれの視点から業務内容を理解することで、全体の流れが明確になります。
ステップ1:見積もりの依頼と提出
まず、発注側が購入したい商品の価格や納期、取引条件などを確認するために、受注側へ見積もりを依頼します。特にBtoB取引では、取引量や時期によって価格が変動するため、このプロセスは不可欠です。受注側は、依頼内容に基づき正確な見積書を作成し、発注側へ提出します。
ステップ2:注文の確定と契約締結
発注側は、受け取った見積書の内容を検討し、条件に合意すれば注文書(発注書)を発行します。受注側がこの注文書を受け取り、内容を確認して注文請書を発行した時点で、法的な契約が成立します。この書類のやり取りが、後のトラブルを防ぐための重要な証拠となります。
ステップ3:商品の発送と受領
契約が成立すると、受注側は納期に合わせて商品を準備し、出荷・納品します。この際、商品に納品書を同梱するのが一般的です。商品を受け取った発注側は、注文通りの品物が正しい数量で届いているかを確認(検品)します。問題がなければ、商品を受領した証として検収書を発行することもあります。
ステップ4:請求と支払い
受注側は、商品の納品が完了したタイミングで、発注側へ請求書を送付します。請求書には、取引内容と金額、支払期日が明記されています。発注側は、期日までに指定された方法で支払いを行い、受注側が入金を確認できれば、一連の取引は完了です。
従来のアナログな受発注業務が抱える4つの課題
電話、FAX、メールなど、従来のアナログな手法に頼った受発注業務は、多くの課題を内包しています。これらの課題は、日々の業務効率を低下させるだけでなく、経営上のリスクにもつながります。
課題1:業務の煩雑化と人的ミスの発生
アナログな業務では、注文内容の聞き間違いや、FAXの文字が不鮮明で読み取れないといった問題が頻発します。また、受け取った注文情報を手作業で社内システムへ転記する際に、入力ミスが発生するリスクが常に伴います。これらのミスは、誤出荷や請求間違いといった重大なトラブルに直結します。
課題2:業務の属人化とブラックボックス化
特定の担当者しか業務の進め方を知らない「属人化」も深刻な課題です。その担当者が不在の場合、業務が完全に停止してしまうリスクがあります。また、個人の経験や勘に頼った業務は標準化が難しく、組織としてのノウハウが蓄積されません。
課題3:リアルタイムな状況把握の難しさ
紙やExcelファイルで受発注情報を管理している場合、全社的な受注状況や在庫情報をリアルタイムで把握することは困難です。情報共有にタイムラグが生じることで、在庫が不足しているにもかかわらず注文を受けてしまうといった、販売機会の損失につながるケースもあります。
課題4:紙の管理コストとセキュリティリスク
大量に発生する注文書や請求書などの帳票を紙で保管するには、ファイリングの手間や保管スペースの確保といった物理的なコストがかかります。さらに、紛失や盗難による情報漏洩のリスクも無視できません。
受発注業務を効率化するポイント
受発注業務を効率化する4つのポイントについて解説します。
業務フローを可視化し、課題を洗い出す
まずは、現状の受発注業務のフローを可視化し、課題がどこにあるか明確化することが重要です。
属人化している業務があると、担当が変わった際や急なお休みの際に、混乱が生じてしまいます。業務を標準化し、マニュアルを作成することで、教育時間の短縮にも繋がります。また、無駄な業務があると、業務負荷が膨らんでしまいます。本来はやらなくてよい業務や、複雑化している業務などの精査が重要です。
システムを見直す
課題解決のために、基幹システムや受発注システム、周辺システムを見直すことは、受発注業務を効率化する方法の一つです。
システムを見直すことで、社員が人力で行っていた受発注業務を効率化したり、自動化したりできます。また、各種システムを自動連携できれば、入力や転記の手間がなくなるだけでなく、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。
アウトソーシングやBPOを活用する
今まで、効率化する方法についてお伝えしてきましたが、「そうは言っても、ノウハウもないし人材も足りない」という場合には、アウトソーシングやBPOサービスの活用も検討するといいでしょう。
アウトソーシングやBPO事業社は各種ノウハウを蓄積しているため、受発注業務の効率化のプロです。自社での人材採用や業務フロー整理の手間を省略できますので、自社の従業員はコア業務に注力したまま、受発注業務を効率化することができます。
受発注システムで実現できることとは?
受発注システムを導入することで、企業は多くのメリットを享受できます。単なる業務効率化に留まらず、経営基盤の強化にもつながる可能性があります。
メリット1:業務自動化による効率向上とミス削減
Web上の管理画面から注文データを直接受け取るため、電話の聞き取りやFAXの転記といった作業が不要になります。データはそのまま販売管理システムなどに連携できるため、手入力によるミスがなくなり、担当者の業務負担を劇的に軽減します。
メリット2:情報の一元管理とリアルタイム共有
受注情報や在庫状況、出荷ステータスといった情報がシステム上で一元管理されます。関係者はいつでも最新の情報をリアルタイムで確認できるため、部門間のスムーズな連携が促進され、迅速な意思決定が可能になります。
メリット3:ペーパーレス化によるコスト削減
注文書や請求書などの帳票を電子データでやり取りするため、紙の使用量や印刷コスト、郵送費、保管スペースといった物理的なコストを大幅に削減できます。2024年1月から本格施行された電子帳簿保存法への対応もスムーズに進められます。
メリット4:取引先との連携強化と満足度向上
発注側は24時間365日、好きなタイミングで注文できるようになり、利便性が大きく向上します。また、迅速かつ正確な納品が可能になることで、取引先からの信頼が高まり、顧客満足度の向上、ひいては長期的な関係構築へとつながります。
受発注システムを選ぶ際の比較ポイント
受発注システムの導入効果を最大化するためには、自社に合ったシステムを慎重に選ぶことが重要です。以下の4つのポイントを比較検討しましょう。
ポイント1:自社の業界・業種への対応実績
食品、アパレル、建設、製造業など、業界によって特有の商習慣が存在します。自社の業界での導入実績が豊富なシステムは、必要な機能が標準で備わっている可能性が高く、スムーズな導入が期待できます。
ポイント2:取引先が使いやすい操作性か
システムは自社だけでなく、取引先にも使ってもらうものです。取引先のITリテラシーに関わらず、誰でも直感的に操作できるシンプルな画面設計であるかは非常に重要です。スマートフォンやタブレットからの発注に対応しているかも確認しましょう。
ポイント3:既存システムとの連携は可能か
すでに社内で販売管理システムや会計ソフトを運用している場合、それらとスムーズにデータ連携できるかを確認する必要があります。API連携などに対応しているシステムであれば、さらなる業務の自動化と効率化が見込めます。
ポイント4:導入後のサポート体制は万全か
システムの導入時だけでなく、運用を開始した後に問題が発生した際のサポート体制も重要です。電話やメールでの問い合わせ窓口はもちろん、操作説明会や定期的なフォローアップなど、手厚いサポートを提供しているベンダーを選ぶと安心です。
受発注を電子化するためのシステム「EDI」
FAXの受発注にともなうストレスは多くの企業で問題視されています。もちろん、昨今のペーパーレス化、業務効率化のニーズにともない、FAXの受発注を電子化する取り組みを行っている企業も少なくありません。
実際に、FAXの受発注を電子化するためのシステムは存在します。EDI(Electronic Data Interchange)やWEB受発注システムです。
EDIとは
EDIは、受発注のほか出荷、請求、支払いといった情報をデータ化し、通信回線を通じて企業間で共有する電子商取引の仕組み・システムを意味します。具体的には以下のようなメリットが期待できます。
「自社と取引先をつなぐツール」という性質上、自社だけでなく取引先も共同で利用することが前提です。詳しくは以下の記事で解説しています。
また、EDIは「従来型EDI」と「WEB-EDI」に分けられます。以下では、それぞれについて簡単にお話ししましょう。
EDIの種類
①従来型EDI
後述するWEB-EDIの台頭にともない、これまでのEDIは「従来型EDI」と呼ばれ区別されています。主に一般の電話回線を通信回線としても用いるEDIです。また、利用する端末には専用ソフトのインストールが必要です。
2024年にはISDNのデータ通信終了が決まっており、従来型EDIからインターネット回線を利用したWEB-EDIへの移行が進むと考えられております。
従来型EDIには以下のような種類があります。
① 個別EDI | 取引先ごとに個別の通信形式・識別コードを用いるEDIです。取引先が増えると追加で通信形式、識別コードを拡張する必要があるため手間がかかります。 |
|---|---|
② 標準EDI | 規格化された通信形式や識別コードを用いて、複数の企業とやり取りできるEDIです。 |
③ 業界VAN | 特定業界に特化したネットワーク技術を用いて、同じ業界内の企業とのやり取りを行うEDIです。標準EDIの一種として分類されています。 |
WEB-EDI
WEB-EDIはインターネット回線を用いてデータのやり取りを行うEDIです。電話回線を利用する従来型EDI以上に高速かつ安定した通信が可能になります。
また、専用ソフトのインストールが不要なので、PCとインターネット回線があればすぐに始められることもメリットと言えます。
\FAX受発注業務の効率化ができる!/
「e-受信FAXサービス」の資料を無料でダウンロードする
受発注業務の電子化を妨げる要因

上述したEDIをはじめ、受発注を効率化するためのサービスは多数展開されています。しかし、魅力を感じていたとしても、自社の判断だけで導入することはできません。また、導入したとしても100%の効果を実感できないこともあります。
ここでは、電子化を妨げる要因や効果を実感できない要因について解説します。
取引先との関係性
EDIの導入に踏み切れるかどうかは、取引先の状況にもよって異なります。取引先が大手であればコストの点から比較的導入が容易です。しかし、取引先には経済的な余裕がない中小企業もふくまれます。こうした企業は、コストをかけてEDIを導入することに消極的な場合があります。
また、業界によっては、世代交代前・文化・風土といった問題から、そもそもシステムに馴染みがないケースもあります。実際には、業界トレンドの変化や取引先の世代交代などを待つしかなく、すぐには導入に踏み切れないことも少なくありません。
「取引先との連絡のために用いる」というツールの性質上、実際に導入する際には自社以外の取引先のことも考えなければならないのです。
システムの乱立
もうひとつ注意しなければならないのが、システムの乱立です。上述したとおりEDIには複数の種類があり、取引先とのやり取りが可能なものを選ぶ必要があります。
取引先ごとに異なるEDIシステムを導入すると、利用するシステムの乱立からかえってやり取りが煩雑になってしまうことも少なくありません。導入するEDIを限定すると一部の取引先とのコミュニケーションのみの効率化にとどまり、期待していたほどの効果が得られないこともあるでしょう。
このように、EDIによる受発注の根本的な効率化を目指すうえでは、一部だけではなく取引先全体と調整を進める必要があります。
受発注の電子化におすすめなサービス
①FAX、WEB画面などが併用できるEDIサービス
EDIのメリットは多いものの、上述したように取引先との調整が難しく導入できないことも少なくありません。発注データをシステムに入力すると取引先へFAX送信されるような、WEB画面とFAXなどの複数手段を併用できるサービスであれば、取引先への負担なく始められるでしょう。
EDI選定の際には、自動FAXサービスとの連携も確認してみるといいでしょう。
FAXでのやり取りを希望する取引先には、コミュニケーションは変わらずFAXで行われるため、取引先への負担はありません。
②OCR・RPA
OCRやRPAも受発注の電子化にはおすすめなサービスです。受信したFAXを、OCR(光学文字認識)技術を使ってテキストデータ化し、基幹システムへの入力処理をRPA(Robotic Process Automation)で自動化すれば、FAXのデータ化や入力処理を効率化できます。
ただし、かすれた文字や傾いた文字などの手書き帳票の場合には識字率が高くない場合もありますので、導入前には実際の帳票を用いてどの程度データ化できるか確認するといいでしょう。
③FAX電子化サービス
FAXを電子化でき、FAXを各自のパソコンで確認し、保存・編集・返信ができる「FAX電子化サービス」の導入もおすすめです。
取引先は従来どおりFAXを使い続けることができるため、取引先へのオペレーション変更を依頼する必要は一切ありません。自社のみでFAX業務の効率化を実施できる点がメリットです。
また、導入コストについても比較的安価なものが多く、導入しやすいといえます。クラウド型のサービスを選べば、万が一運用がうまくいかなかった際の解約もしやすいです。
まとめ
取引先との調整を考えると、FAXの受発注業務をすぐに電子化するのは難しいのが現実です。しかし、FAX電子化サービスを利用すれば、取引先に強いることは何もありません。
***
株式会社ネクスウェイの「FNX e-受信FAXサービス」は、FAX番号を変更せずに利用できる受発注業務に特化したFAX電子化サービスです。専用のアダプタを設置するだけで利用できるため、基幹システムの改修やFAX番号の変更などの手間がかかりません。
非効率はFAX注文を効率化したいものの、FAXをなくすことは難しいとお困りの方は、気軽にお問い合わせください。
>>FAX受発注業務の効率化ができる!
「e-受信FAXサービス」の資料を無料でダウンロードする